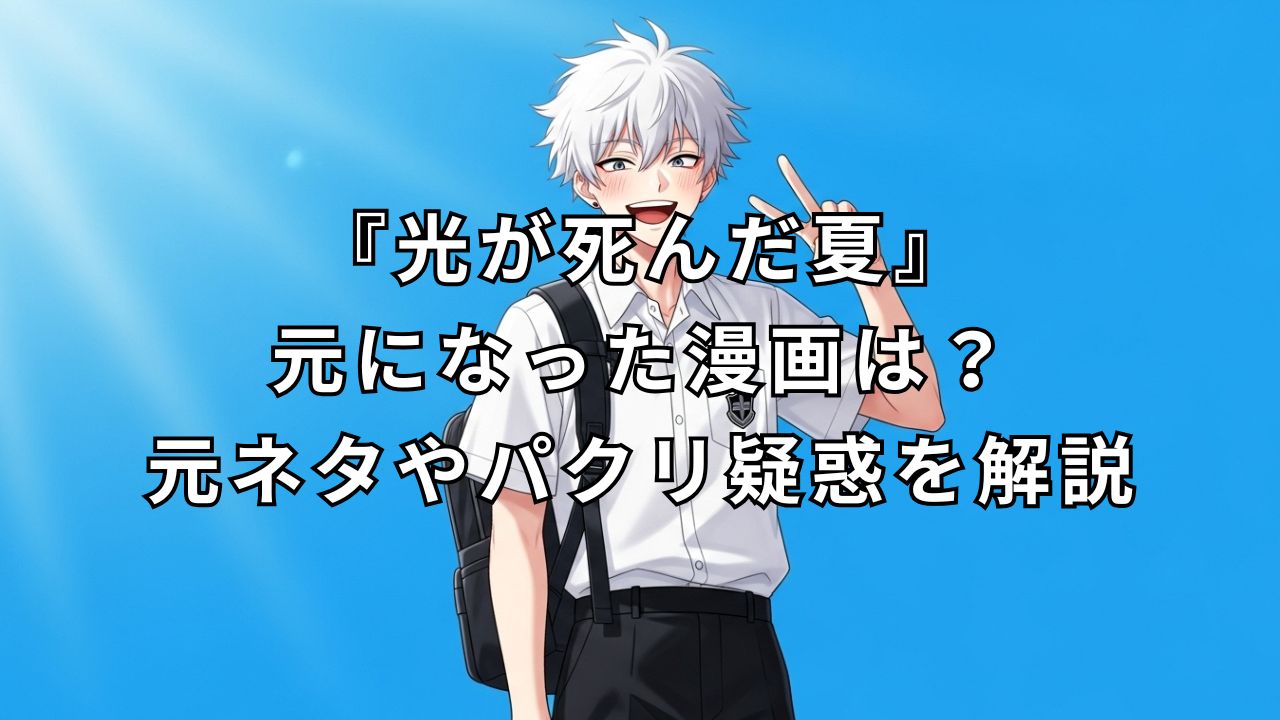『光が死んだ夏』は、その独特な世界観とじわじわと迫る恐怖で、多くの読者を魅了している話題の青春ホラー漫画です。
あまりの人気に、「光が死んだ夏 元になった漫画」と検索して、そのルーツを探している方も多いのではないでしょうか。
また、人気作品であるがゆえに、他作品との「パクリ」疑惑や、BL的な「キス」シーンの有無、「気持ち悪い」といった感想、さらには「バッドエンド」になるのかといった結末の考察まで、様々な疑問やキーワードが飛び交っています。
この記事では、そうした読者の疑問に答えるべく、『光が死んだ夏』の元ネタや原点、そして作品にまつわる様々な謎を、WEBライターとして客観的な情報に基づいて徹底的に解説していきます。
『光が死んだ夏』の元になった漫画と元ネタを解説
『光が死んだ夏』の元ネタはPixivの短編
『光が死んだ夏』に、現在私たちが読むことができる直接的な「元になった漫画」は存在しません。
しかし、物語の原点となったのは、作者のモクモクれん先生が、過去にイラストコミュニケーションサービス「Pixiv」に投稿していた、創作BLの短編作品です。
モクモクれん先生は、もともと漫画家を志していたわけではなく、趣味で絵や物語を創作していました。
コロナ禍で生まれた自由な時間を使い、以前から温めていた構想を漫画という形で表現し、2021年1月にTwitter(現X)とPixivで公開したのです。
この短編が、SNS上で瞬く間に大きな反響を呼び、その才能に注目した複数の出版社の編集者から声がかかったことが、商業連載デビューのきっかけとなりました。
このオリジナルの短編は、人ならざるものと人間の少年との関係を描いた「人外BL」作品であったと、当時の読者からは語られています。
残念ながら、商業化にあたってアカウントが整理されたため、現在この貴重な原点となる作品を読むことはできません。
つまり、『光が死んだ夏』は、元になった特定の漫画が存在するわけではなく、作者の個人的な創作活動から生まれた作品が、商業連載という形で設定や物語を再構築され、私たちの元に届けられた、というのが正確な経緯なのです。
『光が死んだ夏』にパクリ疑惑は本当?
『光が死んだ夏』は、その人気と独特な雰囲気から、一部で他の作品との類似性を指摘する声、特に大人気漫画『チェンソーマン』との「パクリ」を疑う声が上がることがあります。
しかし、結論から言うと、このパクリという疑惑は根拠に乏しいと言えるでしょう。
その理由は、指摘されている類似点が、漫画という表現媒体において、ごく一般的に見られるキャラクター配置や表現手法の範疇に収まるものであり、物語の根幹を成すテーマや世界観は、両作品で全く異なっているためです。
具体的に指摘されるのは、主に登場人物のビジュアル面です。
黒髪で物静かな印象のよしきと、金髪で快活なお調子者のヒカルという主人公コンビの組み合わせが、『チェンソーマン』に登場する早川アキとデンジの関係性を彷彿とさせると言われています。
しかし、このような「物静かな常識人」と「破天荒な行動派」という対照的なキャラクターのバディ(相棒)は、少年漫画や青年漫画の歴史において、数えきれないほど登場してきた王道的な設定です。
これをもって「パクリ」と断定するのは、あまりにも短絡的と言わざるを得ません。
また、作中に見られるグロテスクな描写が共通しているという意見もありますが、これもホラーというジャンルにおいては、ごく一般的な表現手法の一つです。
『光が死んだ夏』が持つ、じっとりとした日本の田舎特有の湿度の高い恐怖演出は、むしろ作者自身のホラー愛好という背景から生まれた、独自の作風と評価するべきでしょう。
『光が死んだ夏』が気持ち悪いと言われる理由
『光が死んだ夏』の感想を調べると、「面白い」という絶賛の声に混じって、一部で「気持ち悪い」というキーワードが見受けられます。
この「気持ち悪さ」の正体は、主に作品が持つ独特のホラー表現と、主人公二人の歪んだ人間関係に起因すると考えられます。
本作の恐怖は、突然お化けが現れて驚かせるような、いわゆる「ジャンプスケア」的なものではありません。
むしろ、ありふれた日常の風景が、静かに、そしてじわじわと「ナニカ」に侵食されていく不気味さや、正体不明の存在への生理的嫌悪感を、巧みに描いている点に特徴があります。
作者のモクモクれん先生は、インタビューでJホラーやPOV(一人称視点)ホラーの熱心なファンであることを公言しており、特に「怖い感じが来る寸前」の、背筋がゾワゾワするような感覚を大切にしていると語っています。
そのため、ショッキングなシーンを直接的に描くのではなく、例えば、描き文字ではない無機質な活字フォントを使った擬音や、まとわりつくような夏の湿気、鳴り響く蝉の声といった、五感に訴えかける演出で、読者の精神をじわじわと追い詰めていきます。
また、物語の根幹にある、親友ヒカルが「ナニカ」にすり替わっていると確信しながらも、その事実から目を背け、関係を続けてしまうよしきの歪んだ執着。
そして、人間の倫理観が通用しない「ナニカ」であるヒカルの、常軌を逸した言動。
これらの健全とは言えない共依存的な関係性が、一部の読者にとっては、生理的な嫌悪感や、まさに「気持ち悪い」と感じさせる大きな要因となっているのです。
「めっちゃ好き」は『光が死んだ夏』の流行語
『光が死んだ夏』を語る上で欠かせないキーワードの一つが、ヒカルのセリフである「めっちゃ好き」です。
この一言は、作品の知名度を飛躍的に高め、特に若い世代にファン層を広げるきっかけとなった、象徴的な流行語と言えるでしょう。
この台詞が爆発的に拡散された背景には、単行本第2巻の発売を記念して企画された、ボイスコミックの存在があります。
2022年10月に公開されたPV企画の第2弾で、ヒカル役を人気声優の下野紘さんが担当。
このボイスコミック内で披露された、下野さんの感情のこもった「めっちゃ好き」という演技が、ヒカルというキャラクターの持つ、子供のような純粋さと、底知れない狂気を完璧に表現しており、多くのファンの心を鷲掴みにしました。
この音声は、特にショート動画プラットフォーム「TikTok」で、二次創作のBGMとして瞬く間に大流行。
キャラクターのコスプレ動画や、漫画の名シーンを再現する動画など、数えきれないほどの関連動画が制作され、Z世代を中心に一大ブームを巻き起こしたのです。
結果として、作品をまだ読んだことがない層にまで、この「めっちゃ好き」という台詞と、『光が死んだ夏』というタイトルが広く認知されることになりました。
一つの台詞が、これほどまでに社会現象となるのは極めて稀なケースであり、作品が持つ強烈な魅力を証明する出来事だったと言えます。
『光が死んだ夏』の元になった漫画以外の疑問を解消
『光が死んだ夏』にキスシーンはある?
結論から申し上げると、2024年5月時点で連載中の『光が死んだ夏』の本編において、主人公のよしきとヒカルがキスをする、という明確なシーンは一度も描かれていません。
しかし、「光が死んだ夏 キス」というキーワードが頻繁に検索されていること自体が、この作品の大きな特徴を物語っています。
その理由は、作中に散りばめられた、二人の絶妙で緊迫した距離感にあります。
本作は、友情以上、恋愛未満ともとれる、よしきとヒカルの極めて濃密な関係性を描いています。
例えば、会話の途中で、思わず息をのむほど互いの顔が異常なまでに接近したり、相手に対する強い執着や独占欲を示すセリフが、不意に交わされたりします。
こうした演出は、読者に「いつ一線を越えてもおかしくない」という、強烈な緊張感と期待感を抱かせます。
特に、ホラー作品特有の「恐怖」によるドキドキと、二人の関係性が進展するかもしれないという「期待」によるドキドキが同時に味わえるため、読者はより深く物語に没入していくのです。
このような、直接的な描写はないものの、読者の想像力を強くかき立てる「匂わせ」の巧みさこそが、「実はキスシーンがあるのでは?」「これから描かれるのでは?」といった、ファンの間での尽きない考察や話題の源泉となっているのです。
『光が死んだ夏』の気まずいシーンとは?
『光が死んだ夏』について調べていると、「気まずいシーン」というキーワードを目にすることがあります。
これは主に、本作が持つBL(ボーイズラブ)的なニュアンスの強い場面を指しており、読者によっては、特に家族や友人と一緒に読む際に、気まずさを感じてしまう可能性があることを示唆しています。
前述の通り、本作の公式なジャンルは「青春ホラー」や「サスペンス」とされています。
しかし、主人公である二人の少年の関係性は、単なる「親友」という言葉だけでは説明がつかないほど、非常に濃密かつウェットに描かれています。
例えば、よしきが、人間ではないヒカルの無防備な姿に、思わず目を逸らして赤面したり、逆にヒカルが、よしきに対して常軌を逸した独占欲を見せつけたりするシーンが、作中には度々登場します。
もちろん、これらの描写は、閉鎖的な田舎町で「二人だけの秘密」を共有せざるを得なくなった、特殊な状況下における、歪んだ共依存関係の表現として解釈することが可能です。
ただ、その友情の範疇を超えているかのような描写の数々が、BLというジャンルに馴染みのない読者や、そうした表現を好まない読者にとっては、「気まずい」と感じるポイントになっていることは事実でしょう。
もし親しい人にこの作品を勧めたいと考えている場合は、こうしたブロマンス(男性同士の親密な関係)の要素が強い作品であることを、事前に伝えておくと、お互いのミスマッチを防ぐことができるかもしれません。
『光が死んだ夏』はどっちが受けか考察
『光が死んだ夏』をBL作品として楽しむファンの間では、「よしきとヒカル、どっちが受けで、どっちが攻めか」という、いわゆる「カップリング」に関する考察が、非常に活発に行われています。
このような議論が白熱する最大の理由は、二人の関係性における主導権が、物語の進行と共に常に揺れ動き、一概に固定的な役割を当てはめることができない、という作品の構造そのものにあります。
物語の序盤では、得体の知れない「ナニカ」であるヒカルが、その人間離れした言動でよしきを翻弄しているように描かれます。
そのため、当初は「ヒカルが攻め」と解釈する読者が多い傾向にあります。
しかし、物語が進展するにつれて、ヒカルを失うこと、そしてヒカルが人間社会で孤立することを恐れるよしきが、時にヒカルを強く束縛し、コントロールしようとするような、力強い言動を見せるようになります。
このことから、「いや、実はよしきの方が攻めなのではないか」という、逆の解釈も生まれてくるのです。
このように、キャラクターの力関係が固定されず、曖昧で流動的に描かれていることが、読者に多様な解釈の余地を与えています。
ファンは、新たなエピソードが公開されるたびに、二人の関係性を再定義し、議論を交わすことになります。
この「答えの出ない考察」こそが、作品をより深く、そして繰り返し楽しむための、重要な要素の一つとなっているのです。
『光が死んだ夏』はバッドエンドになる?
多くの読者が気になっているのが、『光が死んだ夏』がどのような結末を迎えるのか、という点でしょう。
物語全体を覆う不穏な雰囲気や、主人公二人の歪で共依存的な関係性、そして何より、「親友の光が死んで、別のナニカにすり替わった」という、取り返しのつかない絶望的な状況から物語が始まっていることを踏まえると、その結末は、単純なハッピーエンドではなく、「メリバ」あるいは明確な「バッドエンド」になる可能性が高いと考察されています。
「メリバ」とは、「メリーバッドエンド」の略で、登場人物にとっては幸せな結末かもしれないが、客観的に見れば悲劇的、あるいは破滅的である、という特殊な結末を指す言葉です。
例えば、考えられる結末のパターンとして、村に広がる災いを止めるために、ヒカルが自らの命を犠牲にし、よしきが一人残されて絶望するという、明確な「バッドエンド」。
あるいは、ヒカルと共にいることを選んだよしきが、自らも人間であることを捨て、二人だけの世界で永遠に一緒にいることを選ぶ、という結末も考えられます。
後者の場合、よしきとヒカルの「ずっと一緒にいたい」という願いは叶えられるため、二人にとっては幸せな結末(ハッピーエンド)と言えるかもしれません。
しかし、客観的に見れば、それは人間社会からの完全な離脱であり、破滅的な結末(バッドエンド)です。
このような、見る者の立場によって幸福と不幸の解釈が分かれる結末が、「メリバ」にあたります。
作者のモクモクれん先生は、読者に解釈を委ねるような、含みのある描写を多用しているため、誰もが手放しで喜べるような、明快なハッピーエンドを迎える可能性は、残念ながら低いと言えるでしょう。
まとめ:『光が死んだ夏』の元になった漫画と様々な謎
- 『光が死んだ夏』に直接の元になった漫画はない
- 原点は作者がPixivに投稿した創作BL短編である
- 『チェンソーマン』とのパクリ疑惑は根拠に乏しい
- 「気持ち悪い」と言われるのは独特のホラー演出が理由である
- ボイスコミックから「めっちゃ好き」という流行語が生まれた
- 作中に明確なキスシーンは描かれていない
- BL的な「気まずいシーン」は読者の解釈次第である
- 「どっちが受けか」という議論が活発に行われている
- 結末はメリバかバッドエンドになる可能性が高い
- 哲学的テーマや作者の原体験が作品の元ネタとなっている