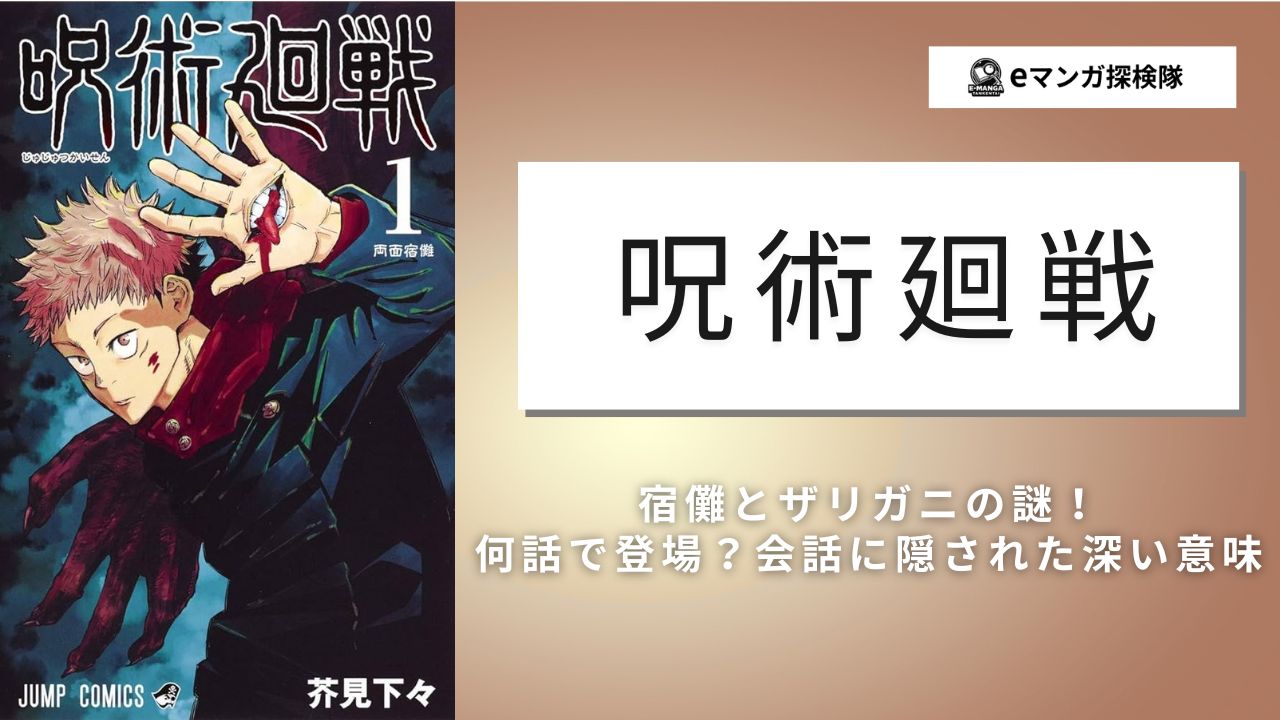『呪術廻戦』の最終決戦、人外魔境新宿決戦のクライマックスで描かれた、あまりにも意外なワンシーン。
主人公・虎杖悠仁が展開した領域の中で、呪いの王・両面宿儺がなんと「ザリガニ釣り」に興じるという、多くの読者を驚かせた場面です。
なぜ最終決戦の最中にザリガニなのか、宿儺はなぜ素直に付き合ったのか。
そして、二人の何気ない会話に隠された、生態系に関する深い問題点とは。
この記事では、大きな話題を呼んだ宿儺とザリガニのシーンについて、登場話数からファンの考察、そして専門家が指摘する問題点まで、あらゆる角度から徹底的に解説していきます。
呪術廻戦の宿儺とザリガニのシーンを解説
宿儺とザリガニのシーンは何話で描かれた?
大きな話題を呼んだ、宿儺と虎杖がザリガニ釣りをするシーンが描かれたのは、漫画『呪術廻戦』の第265話「あの日」です。
週刊少年ジャンプでは、2024年8月5日に発売された2024年36・37合併号に掲載されました。
このエピソードは、人外魔境新宿決戦の最終盤、虎杖悠仁が両面宿儺に対して初めて自身の領域展開を発動した直後の出来事です。
多くの読者が固唾を飲んで見守る中、描かれたのは壮絶な戦闘ではなく、二人が虎杖の故郷である仙台(作中では岩手県北上市周辺がモデル)の心象風景を巡るという、意表を突く展開でした。
その思い出巡りの一環として、幼少期の虎杖が体験したであろうザリガニ釣りのシーンが、宿儺を交えて再現されたのです。
最終決戦の緊張感とのギャップ、そして呪いの王が見せた意外な一面は、読者に強烈なインパクトを与え、掲載直後からSNSなどで大きな議論を巻き起こしました。
虎杖の領域展開でなぜザリガニ釣りをしたのか
虎杖の領域展開の中で、なぜ戦闘ではなくザリガニ釣りのような日常的なシーンが描かれたのか。
それは、虎杖の領域の目的が、相手を殺傷することではなく、「対話」と「自己紹介」にあったためです。
これまでの領域展開とは異なり、虎杖の領域には必殺の効果がありません。
その代わり、領域に引き込んだ相手に、自身の過去や価値観を共有させ、理解を促すという特殊な空間でした。
虎杖は、宿儺に「お前が価値を見出せない、お前以外の人間のことを知ってもらおうと思った」と語っています。
つまり、ザリガニ釣りやアーチェリーといったシーンは、虎杖が幼少期に経験した「たわいのない日常の思い出」そのものです。
これらの体験を宿儺と共有することで、虎杖は「人の命の価値は、大きな役割や偉業にあるのではなく、こうした小さな思い出の欠片にこそ宿る」という自身の死生観を伝えようとしました。
壮絶な戦いの果てに虎杖がたどり着いたのが、力による支配ではなく、対話による相互理解の試みであったこと。
ザリガニ釣りは、その象徴的なシーンとして描かれたのです。
宿儺がザリガニ釣りに付き合った理由の考察
冷酷非道で、自らの快不快のみを行動原理とする宿儺が、なぜ虎杖の思い出巡り、ひいてはザリガニ釣りに素直に応じたのでしょうか。
ファンの間では、いくつかの理由が考察されています。
- 領域の効果が未知数で様子見していた説
最も有力な考察です。虎杖が展開した領域は、これまでのどの領域とも性質が異なり、宿儺ですらその効果を完全には把握できていませんでした。下手に動いて術中にはまることを警戒し、虎杖の出方を見るために、ひとまず「遊び」に付き合ったという見方です。 - 単純に暇つぶしだった説
宿儺は強者との戦い以外には退屈を感じるキャラクターです。漏瑚や万との対話に応じたように、ある種の「暇つぶし」として、虎杖の奇妙な領域に興味を示し、付き合ってやった可能性も考えられます。 - 虎杖という存在への興味・理解のため説
宿儺は虎杖の「百折不撓の理想」に苛立ちを覚えつつも、ある種の興味を抱いていました。虎杖が何を考え、何を伝えようとしているのか。それを理解した上で、完膚なきまでに叩き潰すために、あえて対話のテーブルについたという考察です。
これらの考察から、宿儺の行動は単なる気まぐれではなく、警戒心や好奇心、そして虎杖への執着といった複数の感情が絡み合った、計算高いものであった可能性がうかがえます。
「オマエのアメザリじゃん」の会話が話題に
ザリガニ釣りのシーンで、特にファンの心を掴んだのが、虎杖と宿儺の間の何気ない会話です。
宿儺「小さいな 貴様のは」
虎杖「オマエのアメザリじゃん ニホンザリガニのほうが レアなんだよ」
このやり取りは、まるで親戚の子供と遊ぶおじさんのような、微笑ましい光景です。
これまで絶対的な強者として君臨し、他者を見下してきた宿儺が、ザリガニの大きさでマウントを取るという、非常に人間臭い(?)一面を見せたことに、多くの読者が衝撃と面白さを感じました。
SNSでは、「宿儺様、ザリガニでマウント取ってて可愛い」「親戚のおじさんと甥っ子の戯れ」といった感想が溢れ、二人の関係性の意外な一面として大きな話題となりました。
また、この会話は、宿儺が虎杖の領域内でのルールに則って「遊び」に参加していることを示す重要な描写でもあります。
最終決戦の緊張感の中で描かれたこのシュールで平和な光景は、束の間の癒やしとなると同時に、その後に訪れる決定的な決裂をより一層際立たせる、効果的な演出として機能したのです。
宿儺とザリガニの描写に隠された深い意味
ニホンザリガニとアメリカザリガニの違いとは
虎杖のセリフに登場した「ニホンザリガニ」と「アメリカザリガニ」。
この二種類は、名前は似ていますが、生態や外見、そして日本の生態系における立場が全く異なります。
その違いを理解することが、このシーンの深い意味を読み解く鍵となります。
| 項目 | ニホンザリガニ | アメリカザリガニ |
|---|---|---|
| 分類 | 在来種 | 外来種 |
| 原産地 | 日本 | 北アメリカ |
| 生息地 | 北海道、東北北部の冷たく綺麗な沢など | 日本全国の河川、池、田んぼなど |
| 体長 | 5〜7cm程度 | 8〜12cm程度(大型) |
| 体色 | 暗褐色、茶褐色 | 成体は鮮やかな赤色(幼体は黒っぽい) |
| ハサミ | 小さく、滑らか | 大きく、トゲがある |
| 生態系への影響 | なし(元々日本にいた種) | 水草の食害、水生昆虫の捕食など影響大 |
| 法的規制 | 絶滅危惧Ⅱ類(保護対象) | 条件付特定外来生物(規制対象) |
このように、ニホンザリガニは日本の固有種であり、生息地の破壊などによって数を減らし、今や絶滅が危惧される貴重な生き物です。
一方、アメリカザリガニは食用として持ち込まれたものが野生化し、その旺盛な繁殖力と捕食能力で日本の生態系に大きな影響を与えている外来種です。
作中で虎杖が「ニホンザリガニのほうがレアなんだよ」と言っているのは、この事実に基づいています。
虎杖のセリフが引き起こす生態系の問題点
虎杖と宿儺のザリガニ釣りのシーンは、微笑ましいやり取りとして描かれていますが、実は生態学的な観点から見ると、ある重要な問題点を内包しています。
それは、多くの人が抱いている「小さくて黒っぽいザリガニ=ニホンザリガニ」という誤解です。
実際には、アメリカザリガニの幼体は赤くなく、黒っぽい色をしています。
そのため、アメリカザリガニの子供を、希少なニホンザリガニだと勘違いしてしまうケースが後を絶ちません。
この誤解が引き起こす最大の問題は、アメリカザリガニの生息域拡大です。
もし、アメリカザリガニの幼体をニホンザリガニだと思い込み、「保護しよう」と考えて別の川や池に放流してしまうと、意図せずして生態系を破壊する手助けをしてしまうことになります。
アメリカザリガニは、2023年から「条件付特定外来生物」に指定されており、許可なく野外へ放つことや、販売・頒布することが法律で禁止されています。
作中の虎杖のセリフは、この広く浸透した誤解をそのまま描いたものですが、影響力の大きい作品でこの描写がされることにより、誤解がさらに広まる危険性も指摘されています。
芥見先生がこの問題点を意図して描いたのか、あるいは虎杖の幼少期のリアルな勘違いとして描いたのかは定かではありませんが、このシーンは私たちに外来種問題について考えるきっかけを与えてくれます。
ザリガニシーンが示す虎杖の死生観の変化
ザリガニ釣りのシーンを含む一連の思い出巡りは、主人公・虎杖悠仁の死生観が大きく変化したことを示す、非常に重要な場面です。
物語の序盤、虎杖は祖父・倭助から「オマエは強いから人を助けろ」「大勢に囲まれて死ね」という言葉を託されます。
この言葉は虎杖にとっての「呪い」となり、彼は「正しい死」を求めて戦い続けてきました。
しかし、多くの仲間や罪のない人々の死を目の当たりにする中で、彼の考えは変化していきます。
領域内で宿儺に語った虎杖の言葉が、その変化を象徴しています。
「自分の人生が誰とも繋がらなくて、何も残らなかったとしても、その人を形作る思い出よりも小さな欠片が、どこかを漂っているだけで、人の命に価値はあるんだよ。死に方の問題じゃなかったんだ。」
虎杖は、「どう死ぬか」ではなく「どう生きたか」、そして「生きていることそのもの」に価値を見出すようになったのです。
ザリガニを釣るという、たわいもない、誰の役にも立たないような幼い日の思い出。
しかし、虎杖にとってはそのような小さな記憶の積み重ねこそが、命の価値そのものであると。
この死生観の変化を、最強の存在でありながら命の価値を認めない宿儺に伝えること。
それこそが、虎杖の領域の真の目的であり、ザリガニのシーンは、その新しい価値観を象徴する、ささやかで、しかし力強い描写だったのです。
宿儺の意外な一面とコミュニケーション能力
呪いの王・両面宿儺は、圧倒的な力で他者を蹂躙し、自らの快不快のみを絶対的な基準とする、コミュニケーションとは無縁の存在に見えます。
しかし、虎杖の領域内でザリガニ釣りに付き合ったシーンは、宿儺が持つ意外な一面を浮き彫りにしました。
宿儺は、虎杖の思い出巡りを「下らん」と一蹴しつつも、最後までその対話に付き合っています。
これは、彼が単に相手を無視するのではなく、相手の主張を理解した上で、自身の価値観に基づいて否定するという、高度なコミュニケーションを行っていることを示しています。
振り返れば、宿儺はこれまでも強者や興味深い相手とは対話を楽しんできました。
- 漏瑚に対して:その強さを認め、死に際に「誇れ」と言葉をかけた。
- 万に対して:「愛」という理解不能な感情について、問答を交わした。
- 鹿紫雲一に対して:「強さとは何か」という問いに、自身の哲学を語った。
これらの事実から、宿儺は決して対話不能な怪物ではなく、むしろ他者に強い興味と関心を持ち、自身の価値観をぶつけ合うことを好む、ある種のコミュニケーション強者であるとさえ言えます。
虎杖の領域内で見せた行動も、この一環と捉えることができます。
彼は虎杖の語る「命の価値」を真摯に聞き、理解し、そして「何も感じない」と全力で否定したのです。
この決定的な価値観の断絶を描く上で、ザリガニ釣りのような平和な日常のシーンは、皮肉でありながらも、宿儺のキャラクター性を深く掘り下げるための重要な舞台装置として機能しました。
まとめ:呪術廻戦の宿儺とザリガニのシーンが示すもの
- 宿儺とザリガニのシーンは漫画第265話で描かれた
- 虎杖の領域展開の目的が「対話」であったため、戦闘ではなく思い出巡りが行われた
- 宿儺がザリガニ釣りに付き合ったのは、領域の様子見や虎杖への興味などが理由と考察される
- 二人の微笑ましい会話が、宿儺の意外な一面としてファンの間で話題になった
- 作中で描かれたザリガニは、在来種のニホンザリガニと外来種のアメリカザリガニである
- 虎杖のセリフは、アメリカザリガニの幼体をニホンザリガニと誤認する問題を内包している
- アメリカザリガニは「条件付特定外来生物」であり、安易な放流は生態系を破壊する
- このシーンは、虎杖の死生観が「正しい死」から「生きることの価値」へ変化したことを象徴している
- 宿儺は対話不能な存在ではなく、相手を理解した上で否定する高いコミュニケーション能力を持つ
- ザリガニのシーンは、物語のテーマとキャラクターの深層心理を描く重要な場面であった