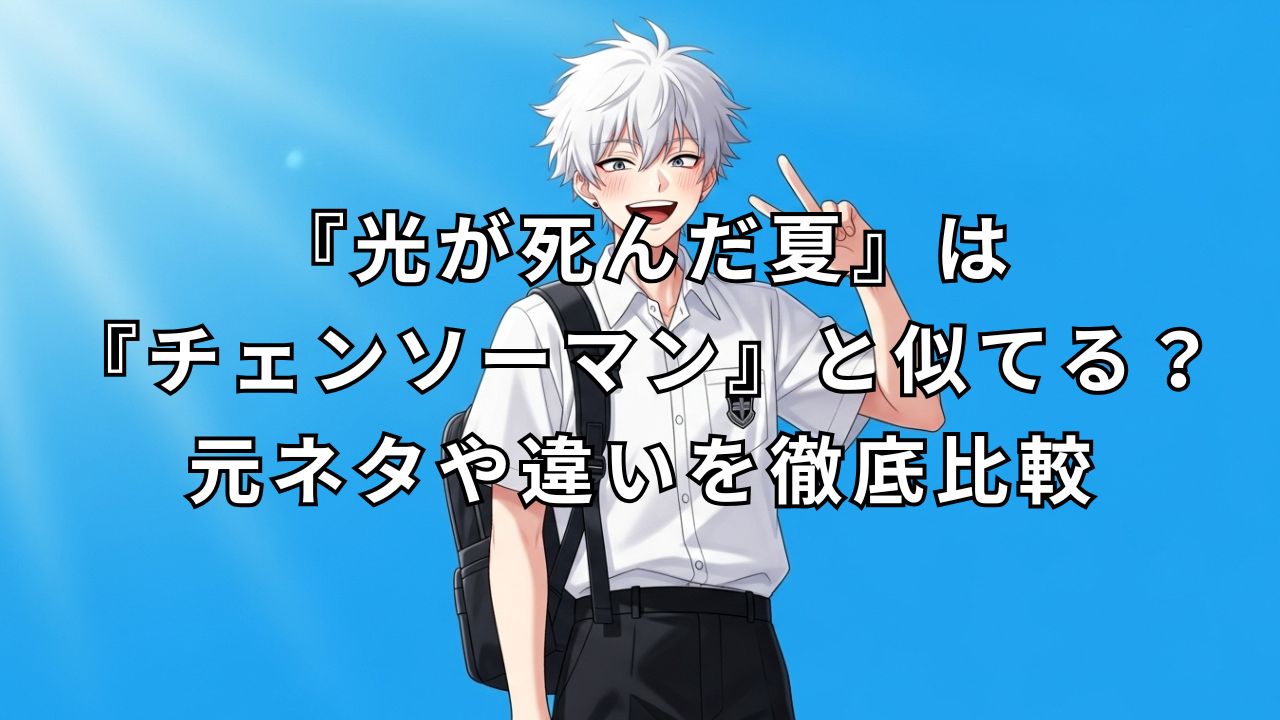話題の漫画『光が死んだ夏』について調べていると、検索候補に必ずと言っていいほど『チェンソーマン』の名前が挙がり、不思議に思ったことはありませんか。
「絵柄が似てるから?」「もしかして元ネタが同じなの?」といった疑問の声は、SNSやレビューサイトでも数多く見られます。
そこでこの記事では、『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』がなぜ比較されるのか、その理由を徹底的に深掘りしていきます。
キャラクターデザインの類似点から、ファンの間で考察される「面白い」という評判の真相、そしてそれぞれの作品が持つ独自の魅力と背景まで、あらゆる角度から二つの物語を比較・考察しました。
この記事を最後まで読めば、両作品が「似て非なるもの」である理由が明確になり、それぞれの持つ唯一無二の魅力に、より一層気づくことができるはずです。
なぜ?『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』が似ていると言われる理由
『光が死んだ夏』のヒカルはデンジに似てる?
結論として、『光が死んだ夏』の主要キャラクターであるヒカルと、『チェンソーマン』の主人公デンジは、外見の第一印象が非常に似ていると言えます。
しかし、これはあくまで表面的な類似点であり、物語を読み進めると両者のキャラクター性や作風は全く異なることがわかります。
なぜ、多くの読者が二人のキャラクターを「似てる」と感じるのでしょうか。
その理由は、金髪(あるいは明るい髪色)、制服姿、そして時折見せるギザ歯といったビジュアル要素が共通している点にあります。
特にコミックスの表紙やカラーイラストで並べてみると、その雰囲気が似ていると感じる方も少なくありません。
実際にSNSやレビューサイトでは、「一瞬チェンソーマンのスピンオフかと思った」「デンジに似てるキャラクターが出てくる漫画」といった声が多数投稿されており、初見で混同してしまう読者が多いことがうかがえます。
一方で、両キャラクターの内面や物語における役割には、明確な違いが存在します。
以下の表で具体的な相違点を比較してみましょう。
| 項目 | ヒカル(光が死んだ夏) | デンジ(チェンソーマン) |
| 性格・本質 | 中身が”ナニカ”に入れ替わっており、人間とは異なる価値観を持つ。よしきへの強い執着心と、正体不明ゆえの不気味さが特徴。 | 非常に貧しい生活から、基本的な欲望(食事、睡眠、女性)に忠実。短絡的で破天荒だが、根は優しく仲間思いな一面も持つ。 |
| 物語での役割 | 静的な恐怖の象徴。穏やかな日常が異質なものに侵食されていく過程で、心理的なサスペンスを生み出す中心人物。 | 動的な恐怖とアクションの象徴。悪魔との壮絶なバトルを繰り広げ、物語をダイナミックに牽引していく原動力。 |
| 絵のタッチ | 作者モクモクれん先生による、繊細で叙情的なタッチ。キャラクターの微細な表情の変化や、美しい背景描写が際立つ。 | 作者・藤本タツキ先生による、荒々しくも力強いタッチ。映画的なコマ割りとスピード感あふれる描写が特徴。 |
このように、ヒカルが「日常に潜む静かな狂気」を体現しているのに対し、デンジは「非日常で繰り広げられる暴力的なカタルシス」を象徴しています。
言ってしまえば、似ているのは外見という「器」だけであり、その中身や描かれ方は対極にあると言っても過言ではありません。
初めは見た目の印象から入ったとしても、それぞれの物語に触れることで、全く異なる魅力を持つキャラクターであることが深く理解できるでしょう。
『光が死んだ夏』の元ネタはチェンソーマン?
『光が死んだ夏』の元ネタが『チェンソーマン』である、という説が一部で囁かれていますが、結論から言うと、その可能性は極めて低いと考えられます。
作者のモクモクれん先生が『チェンソーマン』から直接的な影響を受けたと公言した事実はなく、むしろ作品の根幹には全く別の着想源が存在します。
その理由は、モクモクれん先生がインタビューなどで語っている、作品に影響を与えたものにあります。
先生が特に影響を受けたと公言しているのは、日本の古典的なホラー作品や、哲学的な思考実験です。
作者が影響を公言した作品
モクモクれん先生は、テレビ番組『ほんとにあった怖い話』(ほん怖)や『新耳袋』、そして澤村伊智さんのホラー小説(『ぼぎわんが、来る』など)の大ファンであることを明かしています。
これらの作品に共通するのは、派手なスプラッターではなく、じわじわと日常が侵食されていくような心理的な恐怖、いわゆる「ジャパニーズホラー」の系譜です。
『光が死んだ夏』の、閉鎖的な田舎町を舞台にした湿度の高い不気味さや、説明されすぎない怪異の表現は、まさにこれらの作品から受けた影響が色濃く反映されていると言えるでしょう。
物語の根幹にある「スワンプマン」
さらに、物語の核心的なテーマとして「スワンプマン(沼男)」という哲学的な思考実験が挙げられます。
これは、ある男が沼で雷に打たれて死んでしまい、それと同時に別の場所から、姿形から記憶まで全く同じ存在が生まれてきた場合、その「沼男」は元の男と同一人物と言えるのか?という問いです。
友人であった光(ひかる)が死に、その姿形を模した”ナニカ”がヒカルとして存在する『光が死んだ夏』の物語は、このスワンプマンの思考実験そのものをモチーフにしていると考えられます。
このように、『チェンソーマン』とは異なる明確な着想源が存在することから、元ネタであるとは考えにくいのです。
ただし、『チェンソーマン』の作者・藤本タツキ先生もホラー映画好きで知られており、両作者が同じ「ホラー」というジャンルを愛好している点は共通しています。
同時代に、ホラーという土壌から生まれた二つの傑作が、結果的に似た空気感をまとったと解釈するのが最も自然かもしれません。
知恵袋で見る『光が死んだ夏』は面白い?
Yahoo!知恵袋などのQ&Aサイトで『光が死んだ夏』の評価を調べると、「非常に面白い」という絶賛の声が多数見つかります。
しかしその一方で、「話がよくわからない」「気味が悪い」といった否定的な意見も存在し、読者によって評価が大きく分かれる作品であることがわかります。
結論として、本作は万人受けするタイプの面白さではなく、特定の要素に強く惹かれる読者に深く刺さる魅力を持っています。
面白いと感じる人が評価しているポイントは、主に以下の3つに集約されます。
- 静かで不気味なホラー描写田舎の閉塞的な空気感と、正体不明の怪異が融合することで生まれる、じわじわとした恐怖が高く評価されています。派手な驚かしではなく、日常に潜む違和感や心理的な不安感を巧みに描いている点が、ホラー好きの心を掴んでいます。
- 歪で切ないキャラクターの関係性主人公のよしきが、親友の光(ひかる)が偽物だと知りながらも「一緒にいたい」と願う葛藤。そして、”ナニカ”であるヒカルがよしきに示す純粋で歪んだ執着。この二人の共依存的な関係性が「切ない」「美しい」と多くの読者の心を揺さぶっています。
- 美麗な作画と繊細な表現作者モクモクれん先生の、美麗で繊細な絵柄も大きな魅力です。キャラクターの微細な表情の変化や、光と影を巧みに使った背景描写が、物語の叙情的な雰囲気を高めています。
一方で、面白くない、または理解できないと感じる人々は、これらの魅力的な要素を逆の視点から捉えているようです。
- 「話がよくわからない」という意見は、物語に多くの伏線が散りばめられており、一読しただけでは全体像を把握しにくいというミステリアスな構成に起因します。
- 「ただ気味が悪い」という感想は、心理的な不快感や、時折挟まれる直接的なグロテスク表現が苦手な読者からのものです。
- また、本作が持つ強いブロマンス(男性同士の親密な関係)要素に対して、BL作品に馴染みがない読者が戸惑いを感じるケースも見られます。
このように評価が分かれる作品ではありますが、『このマンガがすごい!2023』オトコ編で堂々の第1位に輝いたという事実は、本作が多くの読者を惹きつけてやまない力を持っていることの何よりの証明と言えるでしょう。
派手なアクションや分かりやすい感動を求めるのではなく、静かな恐怖と切ない人間関係に浸りたい読者にとって、本作は間違いなく「面白い」と感じられるはずです。
比較される?『光が死んだ夏』への海外の反応
結論から言うと、『光が死んだ夏』は海外の漫画・アニメファンの間でも注目度が高まっており、その独特な雰囲気や芸術性が高く評価されています。
日本国内と同様に、『チェンソーマン』のような他の人気ダークファンタジー作品と比較されることもありますが、多くは本作ならではの個性を称賛する声です。
海外で本作が評価されている主な理由は、日本特有の「静かなホラー(Jホラー)」の魅力と、普遍的なテーマである「喪失とアイデンティティ」を巧みに融合させている点にあります。
海外のファンコミュニティやレビューサイトでは、具体的に以下のような反応が見られます。
- 雰囲気とアートスタイルへの絶賛”The atmosphere is incredible and unsettling.” (雰囲気が信じられないほど素晴らしく、そして不穏だ)”The art is breathtakingly beautiful.” (アートが息をのむほど美しい)海外の読者の多くが、まずモクモクれん先生の美麗な作画と、日本の田舎の風景が醸し出すノスタルジックで不気味な雰囲気に魅了されています。光と影のコントラストや、静寂を感じさせるコマ割りが、作品の評価を大きく高めているようです。
- 心理的ホラーとしての評価”It’s a masterful slow-burn psychological horror.” (巧みな、じわじわとくる心理ホラーだ)派手なジャンプスケア(突然驚かせる演出)に頼らず、キャラクターの心理的な揺れ動きや日常に潜む違和感で恐怖を煽る手法は、海外のホラーファンにとって新鮮に映り、高く評価されています。
- アニメ化への期待2025年にアニメ化が発表されて以降、海外での期待感はさらに高まっています。「この独特の空気感をアニメでどう表現するのか楽しみだ」「声優の演技でキャラクターの関係性がどう描かれるのか待ちきれない」といったコメントが数多く寄せられており、アニメ放送をきっかけに、さらに多くの海外ファンを獲得することが予想されます。
『チェンソーマン』との比較については、「どちらもダークなテーマを扱っている」という点で言及されることはありますが、多くのファンは「『チェンソーマン』がハリウッドのアクション映画なら、『光が死んだ夏』は日本のインディペンデント系アートホラー映画のようだ」というように、その作風の明確な違いを認識し、それぞれの魅力を楽しんでいるようです。
『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』それぞれの魅力と背景
『光が死んだ夏』の元になった漫画は存在する?
結論として、商業出版された作品として『光が死んだ夏』の「元になった漫画」は存在しません。
しかし、この物語の原型、いわばルーツとなった作品は存在します。
それは、作者のモクモクれん先生が商業デビューする前に、個人でインターネット上に公開していた短編漫画です。
その経緯は、現代の漫画家が世に出る一つの象徴的なルートと言えるかもしれません。
もともと『光が死んだ夏』の物語の核となるアイデアは、モクモクれん先生がイラスト・漫画投稿サイト「Pixiv」などで発表していた創作BL(ボーイズラブ)の短編作品が起源となっています。
ジャンルは「人外BL」と呼ばれる、人間と人間ならざる者の恋愛や関係性を描くものでした。
当時から先生の個人アカウントをフォローしていたファンの間では、その独創的な世界観と切ないストーリーが非常に印象的な作品として知られていたようです。
この個人制作の短編が、Twitter(現X)などのSNSを通じて多くのユーザーの目に触れ、瞬く間に拡散されて大きな話題となりました。
そして、そのネット上での評判がKADOKAWAの編集者の目に留まり、「ぜひ商業連載を」というオファーに繋がったのです。
まさに、個人の創作活動がSNSというプラットフォームを介して才能を見出され、大きな舞台へと羽ばたいていったという、現代ならではのサクセスストーリーと言えるでしょう。
ただし、注意点として、その原点となった短編作品は、商業連載化が決定した後、作者自身によって削除されています。
そのため、現在そのオリジナル版を読むことはできません。
商業連載にあたっては、より幅広い読者に届けるため、設定やストーリー展開が大幅に練り直され、現在の青年漫画としての『光が死んだ夏』が誕生しました。
ですから、「元になった漫画」は存在しますが、それはあくまで原点・プロトタイプであり、私たちが今読める『光が死んだ夏』は、商業作品として新たに生み出された独立した物語であると理解するのが正確です。
書店ではどこ?『光が死んだ夏』のコーナー
『光が死んだ夏』の単行本を書店で探す際、「一体どのコーナーに行けばいいのか?」と迷ってしまう方は少なくありません。
結論から言うと、最も一般的には「青年コミック」のコーナーに置かれています。
しかし、作品の持つ多様なジャンル性から、店舗によっては他のコーナーで平積みされていることもあります。
なぜ配置場所が書店によって異なるのか、その理由は本作が持つジャンルの多面性にあります。
『光が死んだ夏』は、ホラー、サスペンス、ヒューマンドラマ、そしてブロマンス(BL)といった複数の要素を色濃く内包しているのです。
主な陳列場所
- 青年コミックコーナー本作はKADOKAWAのWebコミックサイト「ヤングエースUP」で連載されているため、分類上は青年コミックとなります。したがって、ほとんどの書店では「青年コミック」の新刊コーナーや、作家名の「ま行」の棚に置かれているのが基本です。まずはこのコーナーを探すのが最も確実でしょう。
- ホラーコミックコーナー物語の根幹をなす「ジャパニーズホラー」の要素を重視する書店では、伊藤潤二作品などのホラー漫画専門の棚に並べられていることがあります。不気味で背筋が凍るような漫画を求めているお客さんに向けて、意図的にこの場所に置かれています。
- 話題書・映像化コーナー「このマンガがすごい!」で第1位を獲得した際や、アニメ化が発表された後などは、ジャンルを問わず最も目立つ平積みの「話題書コーナー」で大々的に展開されることが多くなります。
BLコーナーとの関係は?
「BL(ボーイズラブ)作品なの?」という疑問を持つ方も多いですが、本作は公式にはBL漫画とされていません。
そのため、BL専門のコーナーに置かれることは稀です。
しかし、前述の通り、本作は男性同士の非常に密接で歪んだ関係性を描いており、そのルーツが創作BLにあることも事実です。
このことから、書店員さんの判断で、BLコーナーの近くに「こちらもおすすめ」といった形で関連書として展開されるケースは考えられます。
もし青年コミックの棚で見つからない場合は、話題書コーナーやホラーコーナー、そして念のためBLコーナーの周辺も確認してみると良いかもしれません。
このジャンルの曖昧さ、一言で言い表せない多面性こそが、『光が死んだ夏』という作品の奥深い魅力の一つなのです。
考察!『光が死んだ夏』はどっちが受け?
『光が死んだ夏』を愛読するファンの間で、しばしば熱く議論されるテーマの一つに、「もしBLとして見るなら、よしきとヒカルはどっちが受けでどっちが攻めなのか?」というものがあります。
まず大前提として、本作は公式に「受け」「攻め」が定義されているわけではありません。
しかし、キャラクター間の強い絆や執着を描いた物語であるため、読者が二次創作的な視点でカップリングとして楽しむのは、作品の人気の現れとも言えます。
結論としては、どちらの解釈も成り立つだけの要素が作中に散りばめられており、明確な答えはない、というのが実情です。
ここでは、それぞれの解釈が成り立つ理由を考察してみましょう。
よしきが「受け」と考察される理由
よしきを「受け」と見る意見は、彼の物語における立ち位置に基づいています。
- 受動的な立場: 親友が”ナニカ”に入れ替わるという異常事態に巻き込まれ、ヒカルの存在や行動に振り回されることが多い。物語の展開に対して、受け身の立場にいる時間が長い。
- 精神的な脆さ: ヒカルの正体を知る唯一の人物として、常に恐怖と葛藤を抱えており、精神的に追い詰められている描写が多い。
- 繊細な描写: ヒカルの無防備な寝顔に耳を赤らめたり、その言動に一喜一憂したりと、感情の機微が繊細に描かれており、庇護欲をかき立てられるキャラクターとして解釈されやすい。
ヒカルが「受け」と考察される理由
一方で、ヒカルを「受け」と見る意見も根強く存在します。
- よしきへの依存: 「よしきのそばにいたい」「友達でいてほしい」と強く願い、よしきの承認を求める姿は、関係性において依存的な立場にあると解釈できる。
- 感情的な言動: 人間ではない故の無垢さや純粋さが、時として幼さや危うさとして映る。よしきの前では感情を爆発させ、涙を見せる場面も多い。
- 肉体的な脆弱性(?): 自らの腹を裂いて見せるなど、グロテスクながらも自己を投げ出すような献身的な(あるいは自傷的な)行動が、ある種の受け身的な献身と解釈されることがある。
このように、精神的に追い詰められ受け身に見えるよしきと、よしきに依存し承認を求めるヒカル、どちらの視点に立つかで見え方が大きく変わってきます。
大切なのは、これらはあくまで読者一人ひとりの解釈であり、二次的な楽しみ方の一つであるということです。
公式の答えを求めるのではなく、自分なりのキャラクター解釈を巡らせることが、この作品をより深く味わう醍醐味と言えるかもしれません。
作者モクモクれんとはらだ先生の作風の比較
「暗く、人間の深部に触れるようなドロドロとした物語が好き」という読者の間で、しばしば同時に名前が挙がるのが、『光が死んだ夏』のモクモクれん先生と、『よるとあさの歌』『カラーレシピ』などで知られるBL作家のはらだ先生です。
結論として、両先生は「人間の歪んだ関係性」や「心理的な闇」を描く点で見事に共通していますが、その表現方法や恐怖のアプローチは全く異なります。
両者の作風を比較することで、『光が死んだ夏』が持つ独自の立ち位置がより明確になります。
まず、両先生の作風における共通点は以下の通りです。
- 心を抉る心理描写: 登場人物が抱える劣等感、嫉妬、依存といった負の感情を、容赦なく丁寧に描き出します。
- 単純ではない関係性: 一筋縄ではいかない共依存的なキャラクター同士の関係性が、物語の強い推進力となっています。
- 美しい絵柄とダークな内容のギャップ: どちらの先生も非常に美麗で魅力的な絵柄でありながら、描かれる内容はハードでシリアス。このギャップが読者を引き込みます。
一方で、そのアプローチには明確な違いがあります。
以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | モクモクれん先生(光が死んだ夏) | はらだ先生(カラーレシピなど) |
| 恐怖の種類 | 超常現象、怪談、ジャパニーズホラー。正体不明の”ナニカ”が日常を侵食する、静かでじわじわとくる恐怖。 | 人間の狂気、サイコホラー。人間関係のもつれや愛情の歪みが引き起こす、現実的で生々しい恐怖。 |
| 物語の主軸 | 「異物」との共存と、それに伴うアイデンティティの揺らぎ。ホラー・サスペンスが中心。 | 「人間」同士の愛憎劇。キャラクター間の感情のぶつかり合いと関係性の変化が中心。 |
| 舞台設定 | 閉鎖的な田舎町。外部から遮断された特殊な空間が、物語の不気味さを増幅させる。 | 都会的、現代的。日常的な空間に潜む人間の異常性を描き出す。 |
| 表現の傾向 | 叙情的、静謐(せいひつ)。セリフのないコマや余白を巧みに使い、読者に想像の余地を与える。 | 煽情的、過激。感情が爆発するシーンや、暴力・性的な描写も直接的に描かれることが多い。 |
このように言うと、モクモクれん先生が「静」の恐怖を描くなら、はらだ先生は「動」の恐怖を描く作家と言えるかもしれません。
『光が死んだ夏』が好きな方が、人間の内面に深く切り込むはらだ先生の作品に惹かれるのは自然なことです。
逆に、はらだ先生の描く激しい人間ドラマが好きな方が、『光が死んだ夏』の静かな狂気に新鮮な魅力を感じることもあるでしょう。
どちらも人間の本質に迫る傑作ですが、表現のアプローチが異なることを理解した上で読み比べてみると、それぞれの作品の凄みをより一層感じられるはずです。
まとめ:『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』似てる説の真相
- 『光が死んだ夏』と『チェンソーマン』はキャラの第一印象やダークな雰囲気が似ている
- ヒカルとデンジの外見は似ているが、性格や役割は全く異なる
- 元ネタはチェンソーマンではなく、哲学実験「スワンプマン」や日本のホラー作品である
- 物語の原点は作者が個人で発表していたPixivの短編漫画にある
- 書店では主に「青年コミック」コーナーに置かれることが多い
- 海外でも静かな心理ホラーとして、その独特の雰囲気やアート性が高く評価されている
- 公式にBLではないが、ブロマンス要素から「受け攻め」の二次的考察も活発に行われている
- 静かな恐怖と切ない関係性を描く作風は、一部の読者から熱狂的な支持を得ている
- 『このマンガがすごい!2023』オトコ編1位という客観的な評価も獲得している
- 両作品は似て非なるものであり、それぞれが独立した魅力を持つ傑作である