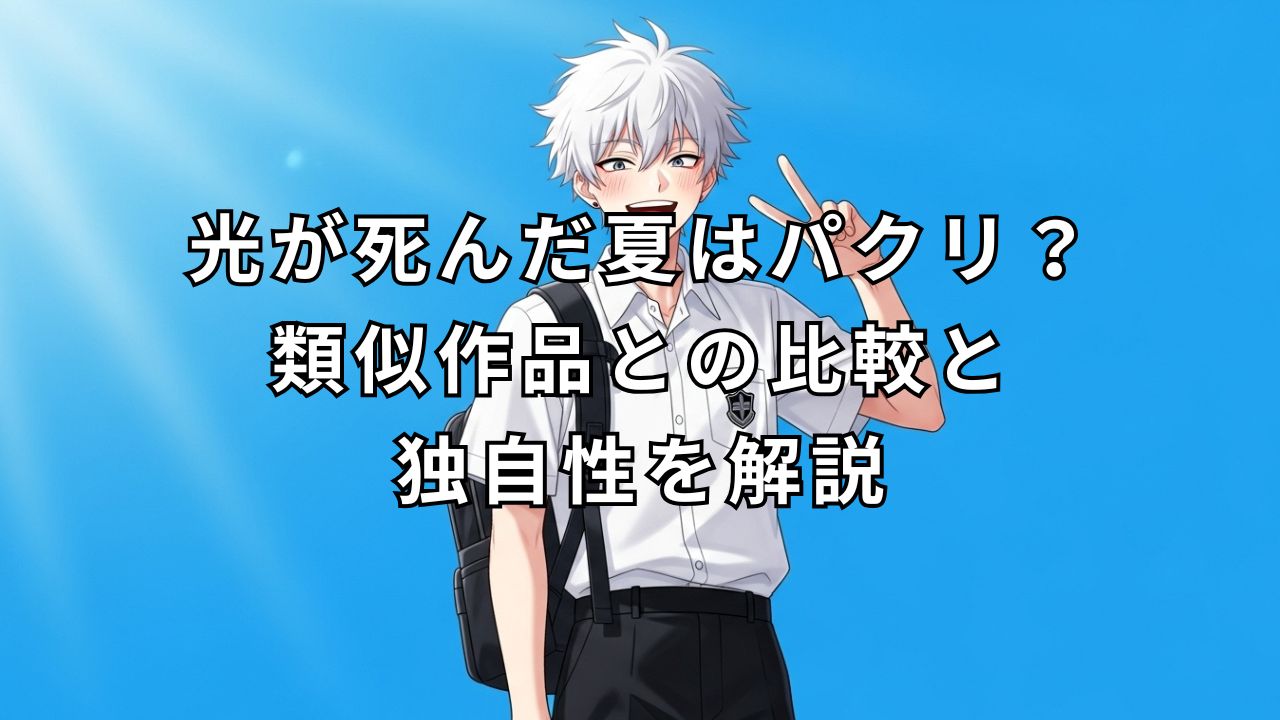「このマンガがすごい!2023」オトコ編で第1位に輝き、累計発行部数300万部を突破するなど、社会現象ともいえる人気を誇る漫画『光が死んだ夏』。
その独特な世界観と忍び寄るような恐怖に多くの読者が魅了されています。
しかし、絶大な人気を誇る作品の宿命か、ネット上では「何かの作品に似てる」「パクリではないか?」といった声が時折見られます。
特に、『チェンソーマン』や『Another』といった人気作との類似性を指摘する意見は少なくありません。
この記事では、『光が死んだ夏』に囁かれるパクリ疑惑の真相について、具体的な比較を交えながら徹底的に検証します。
さらに、作品の根幹をなす哲学的テーマや作者の原体験、元になった作品の経緯などを深掘りし、本作がなぜ多くの読者を惹きつけるのか、その唯一無二の魅力と独自性の根源に迫ります。
『光が死んだ夏』のパクリ疑惑?似てる作品との比較
『チェンソーマン』とのキャラデザや設定の類似点
『光が死んだ夏』のパクリ疑惑を語る上で、最も多く名前が挙がるのが藤本タツキ先生による大人気漫画『チェンソーマン』です。
結論から言うと、両作品のキャラクター造形に似ている点は見られますが、これをパクリと断定するのは難しいでしょう。
その理由は、キャラクターの組み合わせが創作物における王道的な配置であること、そして両作品が描く物語のテーマや方向性が全く異なるからです。
具体的に類似性が指摘されるのは、主要キャラクター2人の関係性です。
- 光が死んだ夏:黒髪で物静かな常識人の「よしき」と、金髪(作中では明るい髪色)で快活、かつ常識が少しズレている「ヒカル」
- チェンソーマン:黒髪で真面目な先輩デビルハンターの「アキ」と、金髪で破天荒、本能のままに動く「デンジ」
このように、落ち着いた黒髪タイプと、活発で少し危うい明るい髪色のタイプというコンビは、読者にキャラクターの関係性を分かりやすく伝えるための定番の組み合わせです。
言ってしまえば、数多くの漫画やアニメ、映画などで採用されてきた「バディもの」の典型的なキャラクター配置であり、これをもって模倣とするのは早計と言えます。
また、グロテスクな描写や不穏な雰囲気が共通しているという意見もあります。
しかし、『光が死んだ夏』が描くのは、閉鎖的な田舎の集落を舞台にした心理的・土着的なJホラーです。
一方、『チェンソーマン』は、悪魔が蔓延る現代社会を舞台にした、スプラッター要素の強いアクション・ダークファンタジー作品です。
恐怖の質や物語のジャンルが根本的に異なるため、表面的なキャラクター配置の類似性だけで「パクリ」と結論づけることはできないでしょう。
『Another』や『寄生獣』との設定の共通点
『チェンソーマン』以外にも、『光が死んだ夏』はいくつかの名作ホラー・SF作品と設定の共通点を指摘されることがあります。
特に、綾辻行人先生のミステリーホラー小説『Another』や、岩明均先生のSF漫画『寄生獣』と似ているという声が見られます。
これらの指摘にも一定の理解はできますが、物語が焦点を当てている部分が大きく異なるため、『光が死んだ夏』は確固たるオリジナリティを確立していると言えます。
『Another』との共通点と相違点
『Another』との共通点は、主に「閉鎖的なコミュニティで起こる怪異」という舞台設定にあります。
- 共通点:
- 田舎町や学校のクラスといった、外部から孤立したコミュニティが舞台。
- コミュニティの中に「人ならざる者」が紛れ込んでいる。
- その存在が引き金となり、不審な死や怪事件が連鎖していく。
しかし、物語の推進力は大きく異なります。
『Another』は、「死者は誰か?」という謎を解き明かし、「災厄」を止める方法を探す本格ミステリーの要素が強い作品です。
一方で『光が死んだ夏』は、怪異の謎解きよりも、親友を失ったよしきの喪失感や、偽物であるヒカルへの歪んだ依存心といった、登場人物の内面的な葛藤に深く焦点を当てています。
『寄生獣』との共通点と相違点
『寄生獣』との共通点は、「日常に侵食する異物」というテーマに見られます。
- 共通点:
- ある日突然、主人公の身近な存在が「人ならざる者」に乗っ取られる。
- 人間と異物が、奇妙な共存関係を築くことになる。
これもまたホラーやSFにおける普遍的なテーマですが、物語の主軸は異なります。
『寄生獣』は、主人公・新一とパラサイト「ミギー」が、他のパラサイトとの生存をかけた戦いを通して、「人間とは何か」「他の生物との共存は可能か」という壮大なテーマを描きます。
対して『光が死んだ夏』は、あくまでよしきとヒカルという二人の関係性に終始します。
ヒカルという「異物」を通して描かれるのは、種族間の生存競争ではなく、「失われた大切な人を取り戻したい」という極めて個人的で切実な願いと、それがもたらす悲劇なのです。
このように、『Another』や『寄生獣』が持つ優れた設定を土台としながらも、物語の焦点を「謎解き」や「バトル」ではなく「個人の内面と関係性」に絞ることで、『光が死んだ夏』は独自の物語世界を築き上げています。
なぜパクリと言われる?人気作ゆえの宿命か
『光が死んだ夏』にパクリ疑惑が浮上する背景には、作品が持つ「王道的な面白さ」と、その「爆発的な人気」が複雑に絡み合っていると考えられます。
多くの読者に支持され、大ヒットとなる作品は、過去の名作と共通する普遍的なテーマや、読者の心を掴むための定番の設定を含んでいることが少なくありません。
『光が死んだ夏』もまた、「親しい人間が入れ替わる」「閉鎖的な村での怪異」といった、ホラーの王道ともいえる要素を巧みに取り入れています。
だからこそ、ホラー作品に詳しい読者ほど「あの作品に似ている」と感じやすい側面があるのです。
しかし、これは決してマイナスなことではありません。
むしろ、先人たちが築き上げてきた「面白い物語の型」をしっかりと踏襲し、その上で新しい魅力を加えているからこそ、本作はこれほどまでに多くの読者の共感を呼んでいると言えるでしょう。
もう一つの大きな要因は、その圧倒的な知名度と人気です。
2024年12月時点でシリーズ累計発行部数は300万部を突破し、「このマンガがすごい!2023」オトコ編で第1位に輝くなど、その勢いはとどまるところを知りません。
特に、TikTokなどのSNSを通じて若者を中心に爆発的に知名度が上がったことで、非常に多様なバックグラウンドを持つ読者の目に触れる機会が増えました。
注目度が高まれば高まるほど、作品に対する様々な意見や感想、時には批判的な視点も生まれやすくなります。
些細な類似点であっても、多くの人が言及することで、あたかも大きな問題であるかのように見えてしまうのは、人気作品が必ず通る道、いわば「人気作ゆえの宿命」とも言える現象なのです。
実際には、これらの指摘は作品の一側面を切り取ったものであり、物語全体を見渡せば、本作が持つ独自のテーマ性や表現がいかに優れているかがわかります。
商業化でBLでなくなったのは本当?
『光が死んだ夏』の背景を語る上で、しばしば話題に上るのが「元々はBL(ボーイズラブ)作品だった」という点です。
そして、その事実から「商業化にあたってBL要素がなくなった」と言われることがありますが、これは半分正しく、半分は誤解を含んでいます。
結論としては、公式のジャンルはBLから変更されましたが、物語の根底に流れる二人の強烈な絆や執着は、むしろ商業化によって、より純度を増して描かれていると言えるでしょう。
Pixivの創作BLから商業連載へ
本作の原点は、作者のモクモクれん先生が、2021年にイラスト投稿サイトPixivやTwitter(現X)で公開していた『光が死んだ夏』というタイトルの創作漫画でした。
この短編は、明確に「創作BL」「人外BL」として投稿されており、その切ない関係性と独特の世界観がSNSで瞬く間に大きな反響を呼びました。
このネット上での人気が出版社の目に留まり、KADOKAWAのWeb漫画サイト「ヤングエースUP」での商業連載へと繋がったのです。
ジャンルの変更とその意味
商業連載版の『光が死んだ夏』は、青年誌レーベルである「角川コミックス・エース」から刊行されており、公式なジャンルは「青春ホラー」「サスペンス」「ブロマンス(男性同士の強い友情)」などとされています。
この変更は、より幅広い読者層、特にBLというジャンルに馴染みのない層にも作品を届けるための商業的な判断であったと考えられます。
しかし、「BLでなくなった」からといって、二人の関係性が薄まったわけでは全くありません。
むしろ、直接的な恋愛描写を削ぎ落としたことで、よしきとヒカルの間に渦巻く、友情とも愛情とも、あるいは共依存ともつかない、分類不可能な感情の機微がより際立つ結果となりました。
「お前が光じゃなくても、俺は…」と葛藤するよしきの姿や、「よしきに好きでいてほしい」という一心で人間を学ぼうとするヒカルの純粋で危険な執着。
これらの描写は、BLという枠組みを超えて、人間の根源的な孤独や承認欲求に訴えかける力を持っています。
結果として、男性読者からも「二人の関係性が尊い」と熱烈な支持を集め、「このマンガがすごい!」オトコ編での第1位獲得に繋がったのです。
「BLでなくなった」のではなく、「ジャンルの枠を超えた普遍的な物語へと昇華された」と捉えるのが、最も的確な表現かもしれません。
『光が死んだ夏』はパクリではない!独自性の根源
哲学的テーマ「スワンプマン」が物語の核
『光が死んだ夏』が、単なるホラー作品に留まらない圧倒的な独自性を放っている最大の理由は、その物語の根幹に「スワンプマン」という哲学的な思考実験を据えている点にあります。
この難解なテーマが、よしきとヒカルの関係性に底知れない深みと切実さを与えているのです。
スワンプマンの思考実験とは?
「スワンプマン(沼男)の思考実験」とは、アメリカの哲学者ドナルド・デイヴィッドソンが提唱した有名な思考実験です。
内容は以下の通りです。
ある男が沼の近くで雷に打たれて死んでしまう。
同時に、すぐそばの沼にも雷が落ち、その化学反応で、死んだ男と原子レベルで寸分違わぬ「コピー(スワンプマン)」が偶然生まれる。
このスワンプマンは、元の男の記憶、性格、友人関係に至るまで全てを完璧に持っている。
彼は何食わぬ顔で元の男の生活に戻るが、果たしてこのスワンプマンは、死んだ男と「同一人物」と言えるだろうか?
物理的には全く同じでも、積み重ねてきた歴史や経験(因果的連続性)が断絶している存在を、私たちは「本人」と認めることができるのか、という非常に難しい問いを投げかけます。
よしきの葛藤とヒカルの探求
『光が死んだ夏』は、この問いを物語そのものにしています。
よしきの目の前にいる「ヒカル」は、まさにスワンプマンです。
姿も声も記憶も、全てが親友・光のもの。
しかし、よしきは直感で「こいつは光ではない」と確信しています。
論理的には拒絶すべき偽物。
それでも、親友を失った喪失感に耐えきれず、よしきはヒカルとの日常を選んでしまいます。
これは、「本物か偽物か」という事実よりも、「そばにいてほしい」という人間の切実な感情が勝ってしまう心の揺らぎを描いており、読者の胸を強く打ちます。
一方で、「スワンプマン」であるヒカル自身も、「自分とは何か」という問いに直面します。
光の記憶は持っていても、それは借り物の過去。
ヒカルは、よしきとの関係性の中で喜びや悲しみ、執着といった感情を学び、「光のコピー」から「ヒカル」という唯一無二の存在へと変化していくのです。
このように、スワンプマンという哲学的な装置を用いることで、本作は「大切な人の死をどう受け入れるか」「自分らしさはどこから来るのか」といった普遍的なテーマを、他に類を見ない深さで描き出しています。
作者の原体験が息づく舞台設定と三重弁
『光が死んだ夏』のもう一つの大きな魅力であり、独自性の源となっているのが、リアリティと不穏な空気が奇妙に同居する舞台設定です。
この説得力のある舞台は、作者モクモクれん先生自身の原体験や記憶から生まれています。
物語の舞台となる「クビタチ」という集落は架空の地名であり、特定の県がモデルになっているわけではありません。
しかし、作中で交わされる方言は「三重弁」を参考にしていることが、公式から明かされています。
YouTubeで公開されたボイスコミックの制作にあたり、三重県出身の声優が方言指導として参加したことがきっかけで判明しました。
作者はインタビューで、関西弁とは少し違う「絶妙なライン」の方言を探していたと語っており、近畿と東海の文化が混ざり合う三重弁の独特の響きが、作品の求める空気感に合致したのでしょう。
「えらい(しんどい、疲れた)」や「〜やん」といった言葉遣いが、閉鎖的な田舎の雰囲気を一層際立たせています。
そして、集落の具体的な風景描写には、作者自身の記憶が色濃く反映されています。
先生は、山と海の境にある集落で唯一の商店を営んでいた祖母の家を訪れた際の記憶が、インスピレーションの源泉であると明かしています。
- 古い磨りガラスの窓
- 黒電話が置かれた部屋
- プライバシーの概念が希薄で、近所の人が勝手に出入りする濃密な人間関係
こうした、どこか懐かしくも息苦しい昭和のノスタルジーを感じさせる風景が、作中の閉鎖的なコミュニティのリアリティを支えています。
読者が感じる「本当にありそう」という感覚は、こうした作者個人のリアルな記憶の断片から紡ぎ出されているのです。
架空の物語でありながら、方言や風景といったディテールに作者の実体験を織り交ぜることで、『光が死んだ夏』は他のどの作品にもない、生々しい手触りのある独自の舞台を作り上げることに成功しています。
原点はPixivで投稿された短編作品
『光が死んだ夏』の誕生経緯は、近年の漫画業界の中でも特にユニークであり、そのプロセス自体が作品の持つオリジナリティを象徴しています。
本作は、出版社主導の企画から生まれたのではなく、作者であるモクモクれん先生が個人でWeb上に発表した一本の短編漫画から全てが始まりました。
2021年、当時まだ商業デビューしていなかったモクモクれん先生は、自身のTwitter(現X)アカウントとイラスト投稿サイトPixivに、同名の短編作品を公開します。
この作品は、明確に「創作BL(ボーイズラブ)」、特に人間と人ならざる者の恋愛を描く「人外BL」のジャンルで投稿されました。
「親友が、別のナニカにすり替わっていたら?」という衝撃的な設定と、二人の痛切な関係を描いたこの短編は、SNS上で瞬く間に拡散され、読者から熱狂的な支持を集めます。
その大きな反響が複数の出版社の目に留まり、争奪戦の末にKADOKAWAの「ヤングエースUP」での商業連載が決定したのです。
この経緯は、いくつかの点で非常に現代的です。
まず、作者の「これを描きたい」という純粋な創作意欲が全ての出発点であること。
そして、SNSというプラットフォームを通じて、作品の魅力がダイレクトに読者に届き、その熱量が商業的な成功へと繋がったという点です。
従来の漫画制作のプロセスとは一線を画すこのサクセスストーリーは、作品の持つ根源的なパワーを証明しています。
商業連載にあたり、前述の通りジャンルは変更されましたが、物語の核となるテーマや二人の関係性は、この個人制作の短編から何一つブレていません。
むしろ、連載という形でより深く掘り下げられています。
こうした誕生の背景を知ることで、『光が死んだ夏』が、流行を計算して作られた作品ではなく、作者の内から湧き出た初期衝動に満ちた、極めて作家性の高い作品であることが理解できるでしょう。
活字フォントを使った独特のホラー演出
『光が死んだ夏』を読んだ人が、まず間違いなく衝撃を受けるのが、その独特な恐怖演出です。
特に、擬音(オノマトペ)の表現方法は、本作のオリジナリティを際立たせる最大の発明と言っても過言ではありません。
一般的な漫画では、物音や心の声などを表現する擬音は、シーンの雰囲気に合わせて手描きでデザインされるのが普通です。
例えば、恐怖シーンであれば、震えるような線や、どろりとしたおどろおどろしい書体が使われます。
しかし、『光が死んだ夏』では、そうした手描きの擬音をあえて使わず、PCで入力したような無機質な「活字フォント(明朝体など)」を多用しているのです。
「ミチ…」「ギ…」「ズル…」
穏やかな田舎の風景や、少年たちの日常会話が描かれるコマの中に、場違いなほどくっきりと、冷たい活字の擬音が配置される。
この表現がもたらす効果は絶大です。
まるで、漫画の世界に不釣り合いな異質なノイズが紛れ込んだかのような、強烈な違和感と不気味さを生み出します。
それは、日常にじわじわと非日常が侵食してくる本作のテーマを、視覚的に完璧に表現した手法です。
作者のモクモクれん先生は、大のホラー好きを公言しており、特に日本のジメっとした空気感を持つJホラーや、主観視点で描かれるPOV(Point of View)ホラーから強い影響を受けていると語っています。
突然の大音量で驚かせるのではなく、静寂の中に響く小さな物音や、理解不能な現象がもたらす「じわじわと精神を蝕む恐怖」。
この活字フォントによる擬音表現は、まさにそうした恐怖の質感を、漫画という媒体で再現するための、計算され尽くした演出なのです。
この独創的な技法は、他のどの作品にも見られない強烈な個性を『光が死んだ夏』に与えており、パクリとは到底言えない、唯一無二の表現力を支える重要な柱となっています。
まとめ:『光が死んだ夏』のパクリ疑惑と独自性の真相
- 『光が死んだ夏』へのパクリ疑惑は存在するが根拠は薄い
- 『チェンソーマン』とはキャラ配置が似ているが物語のテーマは全く異なる
- 『Another』や『寄生獣』とは設定に共通点があるが、物語の焦点が違う
- パクリ疑惑は、作品が持つ王道的な面白さと絶大な人気が背景にある
- 原点はPixivで公開された創作BLであり、商業化でジャンルは変更された
- BL要素はなくとも、二人の強烈な依存関係は物語の核として描かれる
- 哲学的思考実験「スワンプマン」をテーマに据えた点が最大の独自性である
- 舞台設定は作者の原体験に基づき、方言は三重弁を参考にしている
- 活字フォントを使った擬音など、独自のホラー演出が際立っている
- これらの要素から、本作は極めてオリジナリティの高い作品と言える