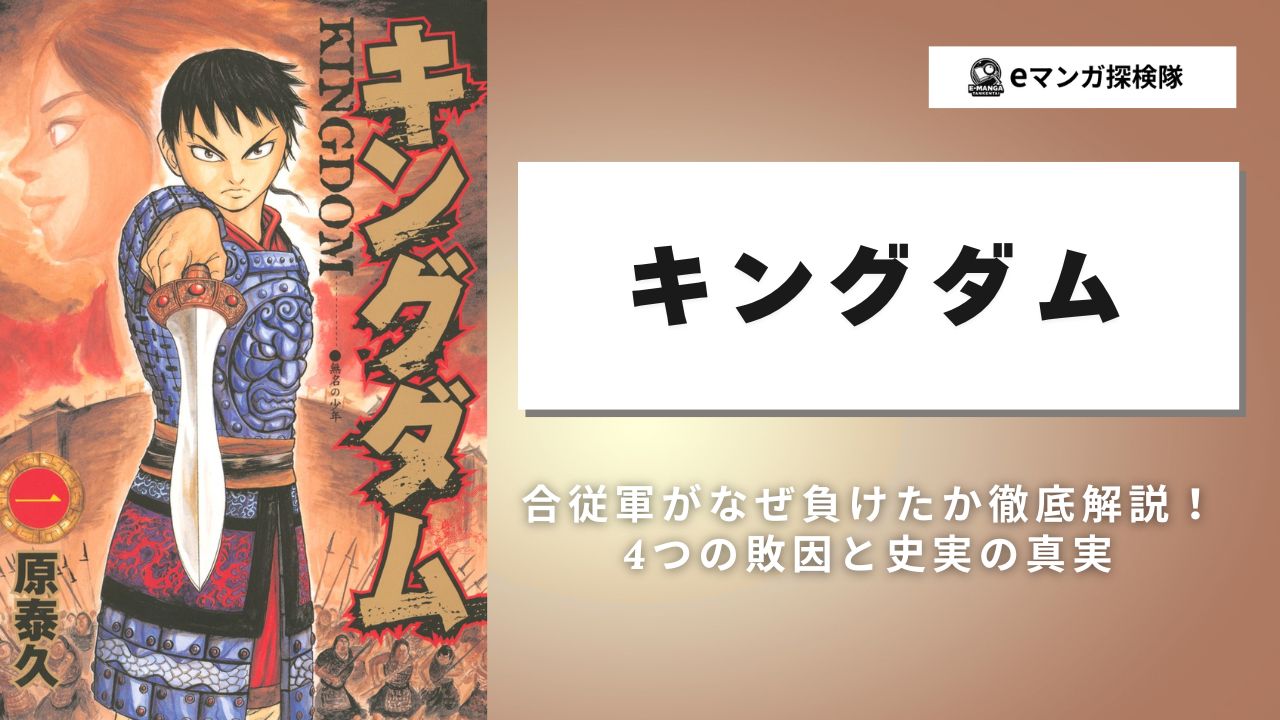キングダムの中でも最大規模の戦いとして描かれる「合従軍編」。
楚、趙、魏、韓、燕の五カ国が連合し、秦国滅亡を目指すという絶体絶命の状況は、多くの読者が手に汗握ったのではないでしょうか。
圧倒的な兵力差にもかかわらず、なぜ強大な合従軍は秦に敗北してしまったのか、その理由について気になる方も多いはずです。
この記事では、キングダムの合従軍がなぜ負けたのか、作中での敗因から史実に基づいた考察、そしてファンの間で語られる様々な疑問まで、網羅的に解説していきます。
【結論】キングダムの合従軍が負けた4つの決定的理由
キングダムにおいて、圧倒的兵力を誇った合従軍が秦国に敗北した理由は、複合的な要因が絡み合っていますが、結論として決定的な理由は主に4つ挙げられます。
それは、秦国側の驚異的な奮戦、蕞(さい)での予想外の展開、合従軍内部の脆さ、そして戦略の根幹を揺るがす「斉」の離反です。
理由1:秦国の将軍たちによる想定外の奮戦と奇策
合従軍の敗因の一つ目は、秦国の将軍たちが見せた個々の能力の高さと、常識を覆す奇策の数々です。
例えば、楚軍との戦いでは蒙武(もうぶ)が武力で大将軍・汗明(かんめい)を討ち取り、騰(とう)が知略と武勇で将軍・臨武君(りんぶくん)を破りました。
函谷関正面では、元野盗の将軍・桓騎(かんき)が奇策を用いて韓軍を混乱させ、大将軍・成恢(せいかい)を討つ大きな戦果を挙げています。
さらに燕軍と対峙した王翦(おうせん)は、巧みな心理戦と罠で敵軍を翻弄し、戦力を無力化しました。
これらの将軍たちの活躍が、合従軍の計画を各個撃破する形で崩していったのです。
理由2:蕞(さい)での秦王・政の覚悟と「山の民」という奇襲
合従軍の敗北を決定づけたのが、函谷関を迂回した李牧(りぼく)の別動隊が攻めた蕞(さい)での攻防戦です。
兵士ではない一般民衆しかいない蕞に、秦王・嬴政(えいせい)自らが駆けつけ、民を鼓舞し共に戦うという覚悟を示しました。
これにより蕞の民は驚異的な粘りを見せ、李牧軍の進軍を食い止めます。
そして最大の決定打となったのが、楊端和(ようたんわ)率いる「山の民」の援軍です。
合従軍にとって全くの想定外であったこの奇襲により、李牧軍は背後を突かれて壊滅的な打撃を受け、撤退を余儀なくされました。
これが合従軍敗北の直接的な引き金となったのです。
理由3:寄せ集めの軍ゆえの連携不足と士気の低下
合従軍は五カ国からなる「寄せ集め」の軍隊であり、その内部的な脆さも大きな敗因でした。
普段は敵国同士であるため、兵士たちの間には憎しみが根強く、完全な統率を取ることは困難を極めます。
総大将である楚の春申君(しゅんしんくん)も、各国の将軍を完全に掌握しきれていたとは言えません。
実際に、楚軍の総大将・汗明が蒙武に討たれた際には、合従軍全体の士気が大きく低下しました。
一つの戦線が崩れると、他の戦線にも動揺が広がりやすいという、連合軍特有の弱点が露呈した形です。
理由4:「斉」の離反による戦略の破綻と背後への懸念
開戦前、秦の外交官・蔡沢(さいたく)の交渉により、合従軍に参加予定だった斉国が離反しました。
これにより合従軍は、秦を攻めている間に自国が斉に攻められるかもしれないという背後への懸念を常に抱えることになります。
この不安要素は、合従軍が短期決戦を強いられる原因となりました。
長期戦に持ち込めば兵站(へいたん)の問題で有利になるはずが、それを選択できなかったのです。
斉の不参加は、合従軍の戦略に大きな制約を与え、結果的に敗北へと繋がる遠因となりました。
【作中での敗因】函谷関・蕞(さい)の戦いを徹底解説
合従軍の敗北は、函谷関と蕞(さい)という二つの戦場で起きた数々の出来事が積み重なった結果です。
ここでは、各戦線で何が起こり、それがどのように敗因へと繋がっていったのかを詳しく解説します。
楚軍の敗北:総大将・汗明の戦死が与えた衝撃
合従軍の主力であった楚軍は、秦の蒙武軍・騰軍と激突しました。
開戦初日には騰が楚の将軍・臨武君を討つという大金星を挙げます。
そして戦いのクライマックスでは、合従軍の武の象徴であった総大将・汗明が、秦の蒙武との壮絶な一騎打ちの末に敗れ、戦死しました。
最強を誇った大将軍の死は、楚軍だけでなく合従軍全体の士気を根底から揺るがし、戦局の流れを大きく秦側へと引き寄せる結果となります。
韓・魏軍の停滞:桓騎の奇策と張唐の壮絶な最期
函谷関の正面を守る秦軍に対し、韓軍と魏軍は兵器を用いて攻め立てました。
特に韓軍の将軍・成恢が用いた毒兵器は秦軍を大いに苦しめます。
しかし、この状況を打開したのが桓騎の奇策でした。
桓騎は敵の兵器を逆利用して地上に降り立ち、少数精鋭で韓軍の本陣を奇襲します。
この作戦に、毒に侵され死を覚悟した老将・張唐(ちょうとう)も同行し、最後の力を振り絞って成恢を討ち取りました。
大将を失った韓軍は機能不全に陥り、合従軍の攻勢はここで大きく停滞することになりました。
燕軍の失態:王翦の策略に翻弄されたオルド
函谷関の側面、山岳地帯では王翦軍が燕軍と対峙しました。
燕の総大将オルドは山の戦いに自信を持っていましたが、王翦の築いた要塞と巧みな罠の前に完全に手玉に取られます。
王翦は意図的に軍を後退させるなどしてオルドを翻弄し、燕軍の精鋭部隊を壊滅させました。
最終的に王翦は、函谷関の裏を狙う楚の別動隊の迎撃にも駆けつけ、合従軍の策を完全に封殺。
オルドは最後まで王翦の掌の上で踊らされ、戦局に何ら貢献できないまま終わりました。
蕞の戦い:李牧の最大の誤算と麃公の死
函谷関の攻防が膠着する中、趙の李牧は精鋭からなる別動隊を率いて秦の首都・咸陽を目指すという本当の狙いを実行に移します。
この動きを唯一察知したのが、本能型の将軍・麃公(ひょうこう)でした。
麃公は信(しん)を率いて李牧軍を追撃しますが、そこに立ちはだかったのが武神・龐煖(ほうけん)です。
麃公は壮絶な一騎打ちの末に命を落としますが、死の間際に信へ「火を絶やすでないぞ」と、未来を託しました。
そして李牧軍が咸陽の手前にある蕞(さい)に到達しますが、そこには秦王・政が民衆と共に待ち構えており、李牧の計画に大きな狂いが生じ始めます。
最終決戦:信vs龐煖の激闘と合従軍の完全撤退
蕞では、秦王・政の檄に応えた民衆と飛信隊の奮闘により、李牧軍は足止めを食らいます。
そして七日目、絶体絶命の状況で楊端和率いる山の民が援軍として出現。
完全に意表を突かれた李牧は、ついに軍の撤退を決断します。
撤退する軍の中で、龐煖は再び信の前に現れ、因縁の対決が繰り広げられました。
満身創痍の信が龐煖に一矢報いたところで決着は持ち越され、龐煖も戦場を去ります。
蕞での敗北報告を受け、函谷関に布陣していた合従軍本隊も全軍撤退を決定し、ここに秦国の勝利が確定しました。
【史実とメタ視点】合従軍が勝てなかった本当の理由
キングダムの物語は史実をベースにしていますが、漫画ならではのドラマチックな脚色が加えられています。
ここでは、史実の記録や物語の構造といった「メタ的な視点」から、合従軍がなぜ勝てなかったのか、その本当の理由を探ります。
史実における函谷関の戦いの記録とは?実はあっけない結末だった
司馬遷の『史記』における「函谷関の戦い」の記述は、実は非常に簡潔です。
「楚、趙、魏、韓、燕の五カ国が合従して秦を攻めたが、函谷関で敗れた」という内容が記されている程度で、漫画で描かれたような各将軍の壮絶な戦いの記録は存在しません。
また、李牧ではなく楚の春申君が総大将であったとされています。
史実では、秦の圧倒的な国力の前に、合従軍は大きな戦果を挙げられずに撤退した、というのが実情に近いようです。
敗因1:天然の要塞「函谷関」という地理的優位性
史実においても、函谷関が難攻不落の「天然の要塞」であったことは、秦にとって大きなアドバンテージでした。
狭い渓谷に作られた関所であり、大軍が一度に攻め寄せることが難しい地形です。
防衛側である秦は、少ない兵力で効率的に敵の攻撃を防ぐことができました。
合従軍が函谷関の突破にこだわった場合、多大な兵力と時間を消耗することは避けられず、この地理的要因が敗北の一因となったと考えられます。
敗因2:長期戦が不可能な遠征軍の兵站(兵糧)問題
合従軍は、各国から長距離を移動してきた「遠征軍」です。
遠征軍にとって最も重要な課題の一つが、兵糧をどう確保するかという兵站(へいたん)の問題です。
戦いが長引けば長引くほど、前線に食料を運び続ける負担は増大します。
一方、自国で戦う秦は兵糧の補給が比較的容易です。
この兵站の差から、合従軍は長期戦に持ち込むことが極めて不利であり、短期決戦で勝負を決める必要がありました。
しかし函谷関の堅牢さがそれを許さず、結果的に撤退せざるを得なかったという側面もあります。
敗因3:物語の制約「史実バリア」という最大の壁
これはメタ的な視点になりますが、キングダムは「秦が中華統一を成し遂げる」という史実に基づいた物語です。
そのため、この合従軍の戦いで秦が滅亡してしまうと、物語そのものが成立しなくなってしまいます。
読者は結末を知っている上で、そこに至るまでの過程を楽しんでいます。
つまり、どれだけ秦が絶体絶命の危機に陥っても、最終的には歴史の通りに勝利するという「史実バリア」が存在するのです。
作者である原泰久先生も、この歴史的な結末に向かって、いかにして秦が勝利したのかというドラマを描いていると言えるでしょう。
合従軍の気になる疑問Q&A|裏切り者・死亡キャラ・戦犯は?
合従軍編はスケールが大きく登場人物も多いため、読者が抱く疑問も様々です。
ここでは、特によく見られる「裏切り者」「項燕の不在」「死亡キャラ」「戦犯」といった疑問について、Q&A形式で解説します。
合従軍の裏切り者は誰?斉が参加しなかった理由とは
作中で「この合従軍には裏切り者がいる」というセリフがありますが、これは合従軍から離反した「斉国」を指しています。
斉は当初、合従軍に参加する予定でしたが、秦の外交官・蔡沢による交渉(多額の賄賂)によって、軍を動かさないことを約束しました。
また、斉は過去に燕の楽毅(がくき)が率いた五カ国合従軍によって滅亡寸前まで追い込まれた苦い経験があり、元々合従軍という仕組みを嫌っていたという背景もあります。
なぜ楚の最強武将・項燕は参戦しなかったのか?
楚には汗明だけでなく、後に秦を大いに苦しめることになる大将軍・項燕(こうえん)がいます。
彼が参戦していれば結果は変わったのではないか、という疑問はもっともです。
これに対する最もシンプルな答えは、「史記」などの元となる史書に、この戦いで項燕が参加したという記録がないためです。
また、各国とも自国の守りを空にするわけにはいかず、最強クラスの武将を一人以上は本国に残していたと考えるのが自然でしょう。
合従軍編で死亡した主要キャラクター一覧
この壮絶な戦いでは、秦・合従軍双方で多くの重要なキャラクターが命を落としました。
以下に主な戦死者をまとめます。
| 国 | キャラクター名 | 役職 | 死因 |
|---|---|---|---|
| 秦 | 麃公(ひょうこう) | 大将軍 | 龐煖との一騎打ちで戦死 |
| 秦 | 張唐(ちょうとう) | 大将軍 | 成恢を討ち取った後、毒により死亡 |
| 楚 | 汗明(かんめい) | 大将軍 | 蒙武との一騎打ちで戦死 |
| 楚 | 臨武君(りんぶくん) | 将軍 | 騰との一騎打ちで戦死 |
| 韓 | 成恢(せいかい) | 大将軍 | 張唐に討たれる |
| 趙 | 万極(まんごく) | 将軍 | 信との一騎打ちで戦死 |
ファンの間で語られる「合従軍の戦犯」は誰?
合従軍敗北の責任が誰にあるのか、という「戦犯」探しはファンの間でよく議論されるテーマです。
最も名前が挙がりやすいのは、王翦に完敗した燕の総大将「オルド」でしょう。
彼は戦局に全く貢献できず、結果的に王翦をフリーにしてしまいました。
また、武の象徴でありながら蒙武に敗れた「汗明」も、士気低下の大きな原因を作ったとして戦犯に挙げられることがあります。
ただし、これらはあくまで物語を楽しむ上での一考察であり、複合的な要因で敗北したと考えるのが妥当です。
まとめ:キングダムの合従軍がなぜ負けたのかを徹底解説
- 合従軍の敗因は複合的だが、主に秦将軍の奮戦、蕞での奇跡、内部の連携不足、斉の離反の4つである
- 蒙武、騰、桓騎、王翦など秦の将軍たちが個々の能力で合従軍を上回った
- 蕞では秦王・政の覚悟と、想定外の「山の民」の援軍が決定打となった
- 普段敵国同士である合従軍は、統率が難しく連携不足という弱点を抱えていた
- 斉が離反したことで、合従軍は背後を警戒する必要があり短期決戦を強いられた
- 楚の総大将・汗明の戦死は、合従軍全体の士気を大きく低下させた
- 史実では、函谷関の戦いは簡潔に記されており、秦の地理的優位性が大きかったとされる
- 遠征軍である合従軍は兵糧問題から長期戦が不可能であった
- 物語の構造上、史実で勝利する秦が負けることはない「史実バリア」が存在する
- 合従軍の「裏切り者」とは、秦の外交交渉に応じて離反した斉国のことである