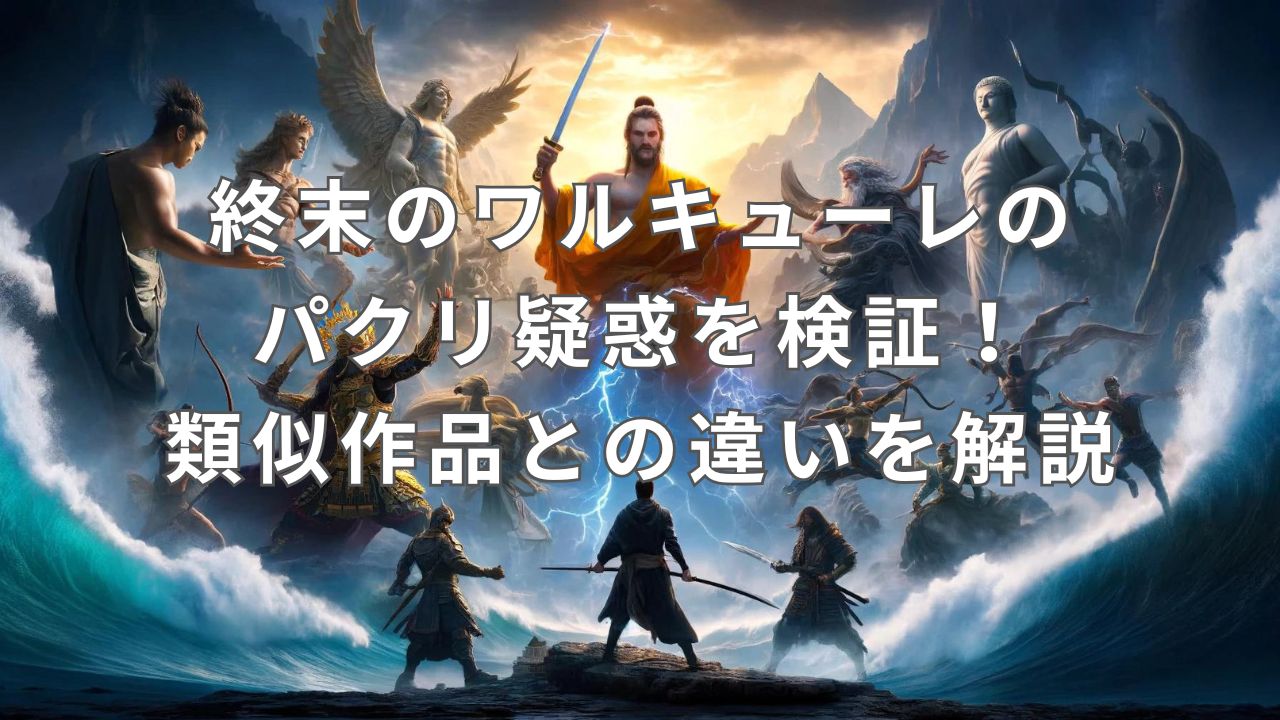連載開始から瞬く間に人気作品となった『終末のワルキューレ』ですが、その人気と同時に「パクリではないか?」という声が聞かれるようになりました。
神々と人類の偉人がタイマンで戦うという壮大な設定は、多くの読者を惹きつける一方で、一部では『Fate』シリーズや『聖闘士星矢』といった他作品との類似性を指摘する意見も見られます。
また、アニメ版に対しては「ひどい」という厳しい評価が下されることもあり、作品の評価は一筋縄ではいかないようです。
この記事では、『終末のワルキューレ』にかけられたパクリ疑惑の真相に迫ります。
類似作品とされる『魔女大戦』や『東京決闘環状戦』などとの比較、現在の勝敗状況、そして本作ならではのオリジナリティについて、網羅的に解説していきます。
終末のワルキューレのパクリ疑惑の真相とは?
終末のワルキューレがひどいと言われる理由
『終末のワルキューレ』が一部で「ひどい」と評価される背景には、主にアニメ版のクオリティに関する問題が存在します。
原作漫画は高い評価を得ている一方で、アニメ版にはいくつかの批判点が寄せられているのが実情です。
最も多く指摘されているのが、作画の問題です。
特にバトルシーンにおいて、動きが少なく静止画を多用した演出が目立ち、「紙芝居のようだ」と揶揄されることがあります。
キャラクターが激しくぶつかり合う迫力あるシーンを期待していた視聴者にとって、アニメーションの躍動感の欠如は大きなマイナスポイントとなりました。
次に、物語のテンポの遅さも批判の対象です。
戦闘中に挿入されるキャラクターの過去を振り返る回想シーンが長い、あるいは観客キャラクターによる解説が多すぎるといった意見が見られます。
これにより、物語の本筋であるバトルがなかなか進まず、視聴者がじれったさを感じてしまうケースがあるようです。
さらに、史実や神話の解釈に対する違和感も理由の一つとして挙げられます。
例えば、史実では残虐な殺人鬼として知られるジャック・ザ・リッパーが、作中では英国紳士として英雄的に描かれるなど、大胆なキャラクター設定に戸惑う声もあります。
また、神々が「~じゃね?」のような現代的で軽い口調で話すことに対し、神としての威厳が感じられないという指摘も少なくありません。
これらの要素が複合的に絡み合い、『終末のワルキューレ』、特にアニメ版に対して「ひどい」という評価が生まれる原因となっていると考えられます。
Fateや聖闘士星矢との類似点と違い
『終末のワルキューレ』のパクリ疑惑を語る上で、最も頻繁に比較対象として挙げられるのが『Fate/stay night』シリーズと『聖闘士星矢』です。
これらの作品と『終末のワルキューレ』には、確かに構造的な共通点が見られますが、同時に明確な違いも存在します。
まず、類似点として指摘されるのは「神話や歴史上の人物をモチーフにしたキャラクターが戦う」という基本設定です。
以下の表で、3作品の共通点と相違点を比較してみましょう。
| 指摘ポイント | 終末のワルキューレ | Fate/stay night | 聖闘士星矢 |
|---|---|---|---|
| バトルの主軸 | 神 vs 人類 | 英霊同士の戦い | 神の力を持つ聖闘士同士の戦い |
| キャラ設定 | 神話・歴史の人物 | 伝説・神話の英霊 | ギリシャ神話ベースの聖闘士 |
| 対戦形式 | タイマン形式×13戦 | マスターとサーヴァントのチーム戦 | 団体戦・師弟関係が主軸 |
| 世界観 | 神界・人間界の交錯 | 現代日本+英霊世界 | 星座・神話ベースの宇宙観 |
このように、大枠の設定には似ている部分があるものの、作品の根幹をなすテーマや対戦形式、演出には大きな違いがあります。
『Fate』シリーズは、魔術師(マスター)と英霊(サーヴァント)がペアを組んで戦う戦略性の高いチームバトルが特徴です。
サーヴァントの能力だけでなく、マスターの策略や心理戦が勝敗を大きく左右します。
一方、『聖闘士星矢』は、女神アテナに仕える聖闘士たちが、仲間との絆や師弟関係を力に変えて戦う団体戦が物語の中心です。
友情・努力・勝利というテーマが色濃く描かれています。
これに対し『終末のワルキューレ』は、神と人類の代表者による「完全タイマン勝負」に徹底的にこだわっています。
1戦ごとのドラマ性と、キャラクターの背景や信念がぶつかり合うバトルの熱量に焦点を当てており、この点が他の2作品との決定的な違いと言えるでしょう。
結論として、これらの作品は同じジャンル内での共通要素を持つものの、それぞれが異なる魅力と独自性を確立しており、『終末のワルキューレ』を単純にパクリと断じることはできないのです。
魔女大戦と終末のワルキューレの関係性
『終末のワルキューレ』としばしば比較される作品に、『魔女大戦 32人の異才の魔女は殺し合う』があります。
この2作品は作者が異なるにもかかわらず、設定や雰囲気が似ていることから、関連性を指摘する声が上がっています。
まず、『魔女大戦』は原作を『賭ケグルイ』で知られる河本ほむら氏、作画を塩塚誠氏が担当しています。
一方、『終末のワルキューレ』は原作を梅村真也氏、構成をフクイタクミ氏、作画をアジチカ氏が手掛けるチーム体制であり、制作陣は全くの別人です。
では、なぜこの2作品は似ていると言われるのでしょうか。
最大の理由は、「歴史上の偉人をトーナメント形式で戦わせる」というプロットが共通している点です。
『終末のワルキューレ』が「神 vs 人類の偉人」であるのに対し、『魔女大戦』は「歴史上の女性偉人同士」が欲望をかけて戦うという設定です。
ジャンヌ・ダルクやクレオパトラ、卑弥呼といった名だたる女性たちが、それぞれの能力を駆使してデスマッチを繰り広げます。
この「偉人バトルロイヤル」というコンセプトが、『終末のワルキューレ』を強く想起させるのです。
また、キャラクターの過去を掘り下げながらバトルが進行していくストーリーテリングや、迫力ある絵柄のタッチも、両作品の類似性を感じる要因の一つかもしれません。
しかし、テーマ性には違いが見られます。
『終末のワルキューレ』が「人類の存亡と尊厳」をかけた戦いであるのに対し、『魔女大戦』は各キャラクターの「強欲」を叶えるための私的な戦いです。
そのため、物語の雰囲気やキャラクターの動機は大きく異なります。
結論として、『魔女大戦』と『終末のワルキューレ』は、作者も出版社も異なる全く別の作品です。
コンセプトに類似性はあるものの、それはアイデアの一致と捉えるのが自然であり、直接的な関係性やパクリといった事実はないと考えるのが妥当でしょう。
ネタバレ注意!終末のワルキューレの勝敗一覧
『終末のワルキューレ』の物語の中核をなすのは、神と人類の存亡をかけた13番勝負「ラグナロク」です。
ここでは、これまでに繰り広げられた激闘の結果を一覧でご紹介します。
まだ読んでいない方にとってはネタバレになりますので、ご注意ください。
| 試合 | 人類代表 | 神代表 | 勝者 |
|---|---|---|---|
| 第1回戦 | 呂布奉先 | トール | 神側 |
| 第2回戦 | アダム | ゼウス | 神側 |
| 第3回戦 | 佐々木小次郎 | ポセイドン | 人類側 |
| 第4回戦 | ジャック・ザ・リッパー | ヘラクレス | 人類側 |
| 第5回戦 | 雷電為右衛門 | シヴァ | 神側 |
| 第6回戦 | 釈迦 | 零福→波旬 | 人類側 |
| 第7回戦 | 始皇帝 | ハデス | 人類側 |
| 第8回戦 | ニコラ・テスラ | ベルゼブブ | 神側 |
| 第9回戦 | レオニダス | アポロン | 神側 |
第9回戦終了時点で、神側が5勝、人類側が4勝という結果になっています。
人類が存続するためには、全13戦のうち7勝する必要があるため、残りの4戦で最低でも3勝しなければならないという、非常に厳しい状況に追い込まれています。
序盤は神側の連勝で絶望的なムードが漂いましたが、佐々木小次郎の歴史的勝利を皮切りに、人類側も一進一退の攻防を繰り広げてきました。
特に、神であるはずの釈迦が人類側として戦うという予想外の展開は、物語に大きな衝撃を与えました。
現在は神側が一歩リードしており、人類にとってはまさに崖っぷちの状況です。
今後、沖田総司やシモ・ヘイヘといった残りの人類代表が、どのような神々と対峙し、この窮地をどう乗り越えていくのか。
一戦一戦が人類の運命を左右する、目が離せない展開が続いています。
終末のワルキューレはパクリ?類似作品と比較
東京決闘環状戦のパクリ疑惑を考察
『終末のワルキューレ』と同じ「月刊コミックゼノン」で連載されている『東京決闘環状戦』もまた、パクリ疑惑が囁かれることがある作品です。
この2作品の類似性は、設定やストーリーよりも、主にビジュアル面、特に単行本の表紙デザインに集中しています。
実際に両作品の表紙を見比べてみると、キャラクターの配置、力強い毛筆体のタイトルロゴ、全体的な構図などが非常に似通っており、一見するとシリーズ作品かと見間違えるほどです。
この酷似したデザインが、「パクリではないか?」という疑惑の最大の根拠となっています。
また、戦闘シーンにおける効果音の描き方や、技が決まった後のテロップ演出など、細かな描写にも共通点が見られます。
しかし、これを単純なパクリと断じるのは早計かもしれません。
両作品が同じ雑誌で連載されているという点が、この問題を考察する上で重要なポイントとなります。
出版社や編集部が、大ヒット作である『終末のワルキューレ』の成功にあやかり、後続作品である『東京決闘環状戦』をヒットさせるためのマーケティング戦略として、意図的にデザインを似せたと考えるのが自然な見方です。
いわば、「ワルキューレ風」のデザインを踏襲することで、書店で読者の目を引き、『終末のワルキューレ』のファン層にアピールする狙いがあったと推測されます。
物語の内容自体は、『終末のワルキューレ』が「神 vs 人類」であるのに対し、『東京決闘環状戦』は「山手線の各駅の代表者が利権をかけて戦う」という全く異なるものです。
したがって、表紙などのビジュアル面での強い影響関係は認められるものの、物語の盗用といった意味でのパクリとは言えず、一種のオマージュや販売戦略と捉えるのが妥当でしょう。
テンゲン英雄大戦のパクリ疑惑も解説
『テンゲン英雄大戦』もまた、「歴史上の英雄が戦う」というコンセプトから、『終末のワルキューレ』との類似性を指摘されることがある作品です。
しかし、こちらの作品については、『終末のワルキューレ』よりもむしろ、平野耕太先生の『ドリフターズ』のパクリではないか、という声がネット上では多く見られます。
まず、『テンゲン英雄大戦』は、織田信長やナポレオン、ジャンヌ・ダルクといった古今東西の英雄たちが、死後の世界で「テンゲン」と呼ばれる神を目指して戦うというストーリーです。
「英雄たちがバトルを繰り広げる」という大枠は『終末のワルキューレ』と共通していますが、物語の構造は大きく異なります。
『終末のワルキューレ』が神々と人類の代表による1対1のトーナメントバトルであるのに対し、『テンゲン英雄大戦』は英雄たちが入り乱れて戦うバトルロイヤル形式です。
この点が、『ドリフターズ』との類似性を強く感じさせる要因となっています。
『ドリフターズ』は、歴史上の英雄たちが「漂流者(ドリフターズ)」と「廃棄物(エンズ)」という二つの勢力に分かれ、異世界で国盗り合戦を繰り広げるという物語です。
英雄たちが異世界に召喚され、集団で戦うというプロットが『テンゲン英雄大戦』と非常に似ています。
このように、『テンゲン英雄大戦』は、『終末のワルキューレ』とは「タイマン勝負」か「バトルロイヤル」かという点で明確な違いがあります。
むしろ、英雄たちが異世界で集団戦を行うという点において『ドリフターズ』との共通点が多く、パクリ疑惑が議論される際は、主に『ドリフターズ』との比較で語られるのが現状です。
終末のワルキューレにギルガメッシュは登場?
『終末のワルキューレ』のファンや、『Fate』シリーズのファンの間で、しばしば話題に上るのが「ギルガメッシュは登場するのか?」という疑問です。
結論から言うと、2025年現在、原作漫画およびアニメの『終末のワルキューレ』に、ギルガメッシュ王は登場していません。
では、なぜ彼の登場がこれほどまでに期待され、噂されるのでしょうか。
その理由は、主に二つ考えられます。
一つは、ギルガメッシュが人類最古の叙事詩『ギルガメシュ叙事詩』に登場する伝説的な王であり、「人類最古の英雄」として抜群の知名度とカリスマ性を持っているためです。
神々に匹敵する力を持っていたとされる彼の存在は、『終末のワルキューレ』の「神 vs 人類最強の偉人」というコンセプトに完璧に合致しており、ファンが彼の参戦を期待するのは自然なことでしょう。
もう一つの大きな理由は、TYPE-MOONの『Fate』シリーズにおける絶対的な人気キャラクターとしての地位です。
『Fate』シリーズで「英雄王」として描かれるギルガメッシュは、最強クラスのサーヴァントとして圧倒的な存在感を放っています。
このため、『Fate』シリーズのファンが、『終末のワルキューレ』の世界でも彼の活躍を見たいと願う声が多く上がっているのです。
このような背景から、公式では登場していないにもかかわらず、ファンの間では彼の参戦を予想する声や、二次創作での活躍が絶えません。
特に「小説家になろう」などのウェブ小説投稿サイトでは、『終末のワルキューレ』と『Fate』のクロスオーバー作品が数多く投稿されており、その多くでギルガメッシュが人類代表の一人として神々と激闘を繰り広げています。
公式での登場は未定ですが、彼の存在はファンの想像力を掻き立てる、特別なキャラクターであると言えます。
神VS人類の構図とオリジナリティ
『終末のワルキューレ』が多くの類似作品と比較されながらも、独自の輝きを放ち続けている最大の理由は、その根幹をなす「神 VS 人類」という構図そのものにあります。
この大胆な設定こそが、本作最大のオリジナリティであり、物語に深いテーマ性を与えているのです。
単なる異能力バトル漫画と一線を画すのは、絶対的な存在である「神」に対し、本来は非力で寿命も短い「人類」が、種の存亡と尊厳をかけて一歩も引かずに立ち向かうというドラマ性にあります。
この一見無謀な戦いの中に、読者は人類の持つ無限の可能性や、逆境に屈しない精神の気高さを見出し、心を揺さぶられるのです。
物語の冒頭、神々が下した人類への終末の判決に対し、戦乙女(ワルキューレ)のブリュンヒルデが「闘いで決着をつけるべき」と異を唱える場面は、単なるバトル提案ではありません。
それは、一方的な裁きに対する抵抗であり、人間という存在そのものへの信頼と誇りの表明でもあります。
この構図は、理不尽な力に屈せず声を上げることの重要性や、多様な歴史や文化を持つ人類全体への敬意といった、現代社会にも通じるメッセージを内包しています。
さらに、本作のオリジナリティを際立たせているのが、「神器錬成(ヴェルンド)」というシステムです。
これは、人類代表の闘士が、13人の戦乙女のいずれかと一体化し、その身を武器に変えて神々と戦うという設定です。
単なるパワーアップではなく、戦乙女との絆や、彼女たちの命をも背負って戦うという重みが加わることで、一戦一戦に深い精神性が生まれます。
各闘士の史実や逸話に基づいた背景描写と、この神器錬成システムが組み合わさることで、キャラクターの生き様や信念が色濃く反映された、唯一無二のバトルが展開されるのです。
これらの要素により、『終末のワルキューレ』は、たとえ設定が似た作品があったとしても、決して埋もれることのない、確固たるオリジナリティを確立しています。
まとめ:終末のワルキューレのパクリ疑惑と独自性の真相
- 『終末のワルキューレ』のパクリ疑惑は『Fate』などとの設定の類似性が主な原因である
- しかし対戦形式やテーマ性が異なり、明確な独自性を持つ
- アニメ版が「ひどい」と評されるのは、主に作画や物語のテンポの問題である
- 『魔女大戦』や『東京決闘環状戦』も類似性が指摘されるが、それぞれ異なる作品である
- 『東京決闘環状戦』との表紙の類似は、出版社の販売戦略の可能性が高い
- 現在の勝敗は神側5勝、人類側4勝と人類が追い詰められている
- 英雄王ギルガメッシュは公式には登場せず、二次創作で人気を博している
- 「神VS人類」という基本構図こそが、本作最大のオリジナリティである
- 「神器錬成(ヴェルンド)」というシステムが、バトルに深みと独自性を与えている
- 結論として、パクリではなく、多くの独自要素を持つオリジナリティの高い作品と言える